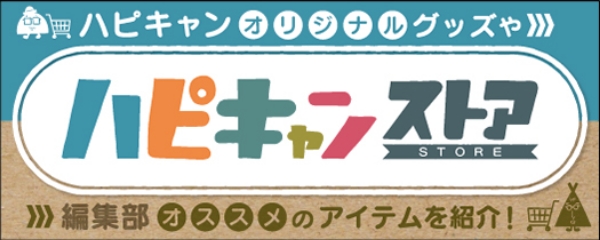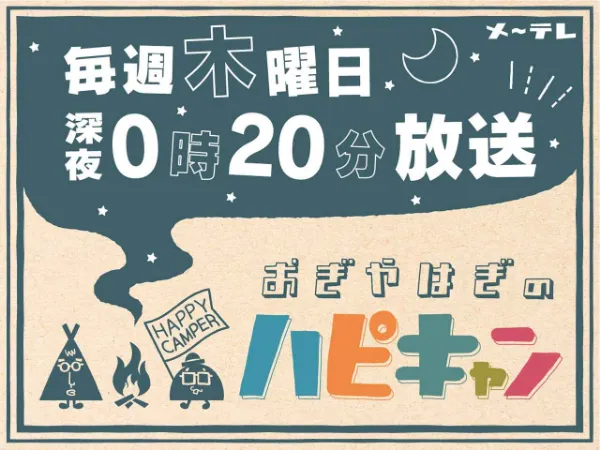「おぎやはぎのハピキャン(メ~テレ制作)」シーズン12のプレゼンキャンパーは芸能界きってのキャンプの達人、うしろシティ阿諏訪泰義さん。番組で登場したテクニックの一つ、フェザースティックは、ナイフで木を削り着火剤として使う、ブッシュクラフトの基本テクニックです。着火剤いらずで焚き火を始められる、フェザースティックの作り方についてご説明します!
番組ロケの様子はこちらから
YouTubeで本編動画まるごと配信中です!
阿諏訪流ブッシュクラフトキャンプ 第1話「おぎやはぎのハピキャン」【おぎやはぎ】【阿諏訪泰義】【DJ松永】
www.youtube.com【フェザースティックとは?】木の表面を毛羽立たせ火がつきやすくなる 着火剤不要に

Photographer 吉田 達史
フェザースティックとは、木の表面を削って鳥の羽根(フェザー)のように毛羽立たせて、火が着きやすい状態に加工するテクニックです。ナイフと木、火種さえあれば着火剤を使わなくても焚き火ができるようになります。
木が多少湿っていても削ることで乾燥面を出し、酸素にも触れやすくなるため、木をそのまま燃やすより炎が上がりやすくなります。落ちている木を拾って使うと乾いているとは限りませんので、ブッシュクラフトでは多用されます。
もちろんキャンプで普通に焚き火をする際にも、使える技ですよ!必要に駆られてというよりは、火遊びの一つとして楽しむキャンパーも多いですね。
【フェザースティック作りに必要なもの】ナイフ・薪・革手袋の3点 オススメをご紹介

Photographer 吉田 達史
1)木を削るためのナイフ
フェザースティック作りに必要なものですが、まずは木を削るためのナイフ。折り畳みナイフやカッターなどでも削ることは可能です。刃が小さいものの方が、慣れていなくても扱いやすいので削りやすいと言えます。
実際のキャンプなどでは、バトニングからの流れでフェザースティックを作ることが多くなります。刃が薄いナイフや折り畳みナイフはバトニングに向いていないため、複数のナイフに持ち替える手間を考えますと、バトニングに使ったナイフをそのまま使うことになるでしょう。

筆者撮影
2)材料の薪 針葉樹がおすすめ
フェザースティックの材料となる薪。直径2~3cm前後、初めのうちは角材のように角がある方が削りやすいです。太い薪しかなければ、バトニングで小割にしましょう。
薪はバトニングと同様に、木目が真っ直ぐな針葉樹が削りやすいです。
3)革手袋
その他あると良いものとして、革手袋。手が滑った時に怪我しにくくなるのはもちろん、滑っていなくても薪を握った時にささくれが指に刺さりやすいです。キャンプ中に刺さると地味に痛く、ピンセットが無いとなかなか抜けにくいですよ。

筆者撮影:革手袋と軍手
熱くなるわけではないので、手が保護できて滑りにくいものなら革製でなくとも構いません。バトニングして、フェザースティックを作って、火を着けて焚き火...という流れになることを考えますと、ある程度の耐熱性があるものなら付け替えずに済みます。

作業に使っていると必ず汚れるものなので、安価な手袋で構いません。耐熱性が高いグローブほど分厚くなりますが、ナイフを握りにくくなります。上記リンクのような革製ワークグローブがバランスが良く、おすすめです。