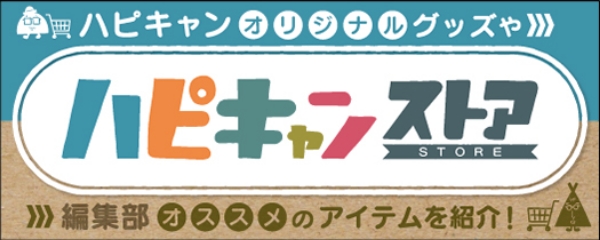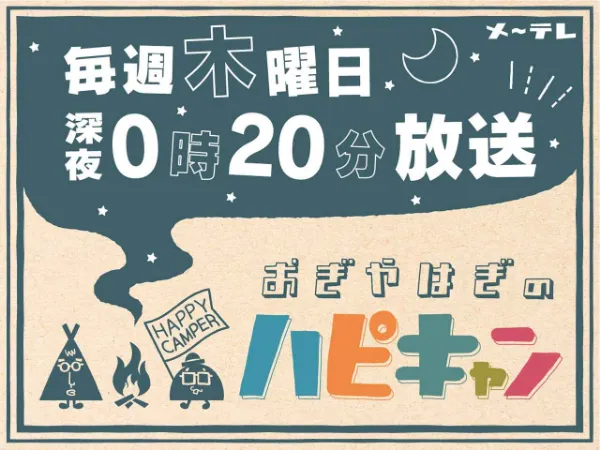直火が禁止されているキャンプ場で焚き火をするには、焚き火台が必要になります。焚き火台は形状やサイズなど種類が様々で、中には「自分で作れるかも…?」 と思えるものも。今回は焚き火台の種類と、実際に筆者が作った焚き火台の製作手順もご紹介します。
- この記事をシェア
-

-

-

-

-
手本にする焚き火台を決めよう! メッシュ・ウッドストーブ・コンパクト・BBQグリルなど
キャンプで使う焚き火台は色々な形状がありますが、まずはお手本にする焚き火台の種類を決めましょう。
大きく分類すると、以下のような5つのタイプに分かれます。
1. メッシュタイプ
●UNIFLAME ユニフレーム ファイアスタンドII /683064 【UNI-BBQF】
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載していますユニフレーム UNIFLAME /ファイアスタンドII 特殊耐熱鋼メッシュを採用し、巻いてたためるコンパクトな焚火台。ツーリングやバックパッキングにも携帯できる軽量490g。メッシュの網目は0.96mm目、火が落ちることはほとんどありません。【サイズ】使用サイズ:約400×400×300(高さ)mm収納サイズ:約φ60×570mm【材質】メッシュシート:特殊耐熱鋼FCHW2スタンド:ステンレス鋼【重量】 約490g【付属品】 収納ケース※モニタやPC環境等により実物と多少色合いが異なって見える場合もございます。※自社ホームペー…
¥ 6,400
2021-06-20 11:24
薪を置く場所がメッシュ(網)になっているタイプです。筆者が最初に作った焚き火台がこのタイプでした。
お手本にしたのはユニフレーム(UNIFLAME)の「ファイアスタンド」です。
ポール4本をクロスさせて脚を固定し、その上に薄いメッシュ網を乗せて薪を置くだけの簡単構造です。のちほど作り方もご説明します。
2. ウッドストーブタイプ
Lixada ウッドストーブ ピクニック バーベキューコンロ 焚火台 ファイアスタンド 折りたたみ 薪 ウッドストーブ アウトドアストーブ 組立簡単 コンパクト 軽量 収納袋
優れた材質:ステンレス鋼素材で作ったので、タッチオープンを二台載せても問題なく使用できます。頑丈なスタンドを使用しており、分散耐荷重は10kgとなります。変形しにくい仕様ですね。耐久性も高く、長く使いいただけます。最新的なデザイン:通気性に優れた空気穴のあいたパネルで燃焼を促進します。燃料追加に便利な開口部で、アルコール、薪、炭などの燃料源が好みます。炊飯やちょっとした料理、お湯を沸かすことも可能です。組み立て式:お手入れは簡単なステンレスタイプで、複雑な組立は一切なく、10秒で簡単に組み立てできます。収納袋もついており、カバンなどにも入れます。野外BBQ等のアウトドアー活動で大人気なパ…
¥ 3,629
2021-01-29 19:45
主に、小枝や木端を燃やして使うタイプの焚き火台です。
形状は丸型、三角形~六角形などがあります。
大きさは縦横15cm前後、高さは15cm~20cmほどのものが多く、ソロキャンプに適したサイズです。
3. コンパクトグリルタイプ
www.amazon.co.jpこちらはソロキャンプや卓上で使うサイズで、調理用も兼ねる焚き火台です。ステンレスの板など熱に強い素材の板を箱型に組み、焼き網を乗せて使います。
2~3段の高さ調節ができる構造が多く、使う燃料の大きさに応じて受け板の高さを調節します。使う燃料は薪や炭が一般的です。
筆者が2番目に作ったのがこのタイプで、現在も使用中です。こちらも、のちほど作り方を詳しくご紹介しますね。
折りたたみ B6 バーベキューコンロ スマートグリル B6型 コンパクト 焚火台 焚き火台 一人用 小型 カマド キャンプ アウトドア 1台3役 高さ調節
■商品説明 【 使い方は自由自在 】 五徳と網がセットのバーベキューコンロ。 グリル、煮炊き、焼き物料理だけでなく、風防板としても使用できるマルチタイプ。 【 高効率燃焼 】 本体は錆びにくいステンレス製。 側面及び背面の空気孔が継続的な空気循環を促し、燃焼効率をアップ。 調理時間の短縮、燃料の節約に繋がります。 【 簡単組立 】 誰でも簡単に組み立てられるシンプル仕様。 組立手順が少なく、後片付けも素早く行えます。 【 折り畳みコンパクト 】 ポータブルサイズで持ち運びができる折りたたみ式デザイン。 専用収納袋付きで、コンパクトに収納できます。 セット内容:本体フレーム、炭受け、五徳…
¥ 2,000
2021-01-29 19:48
4. 超コンパクトタイプ
STC社 Picogrill 398 (ピコグリル 398) スピット(串) 2本付属 焚き火台 ネイチャーストーブ 【並行輸入品】
◆商品名:STC社 Picogrill 398 (ピコグリル 398) スピット(串) 2本付属 焚き火台 ネイチャーストーブ 【並行輸入品】 スイス STC社 ピコグリル398 ストーブ本体、スピット(串) 2本、収納ケース サイズ: 収納時 33.5cm×23.5cm×1cm 組立時 38.5cm×26cm×24.5cm 材質:ステンレス 本体重量:約450g スイス STC社 ピコグリル398 ストーブ本体、スピット(串) 2本、収納ケース サイズ: 収納時 33.5cm×23.5cm×1cm 組立時 38.5cm×26cm×24.5cm 材質:ステンレス 本体重量:約450g
¥ 18,340
2021-01-29 19:51
薄型の超軽量タイプで、細い鉄棒やステンレスポールなどを脚にして、その間に薪受け用の薄い金属板を渡して使います。
コンパクトに収納できる、ソロキャンプ向けの焚き火台です。
5. BBQグリルタイプ
【1,000円OFFクーポン配信中】ユニフレーム 焚き火台 ファイアグリル キャンプ 焚火 BBQ アウトドア お1人様1点限り
簡単な組み立てでコンパクトな収納! 焚き火グッズ:焚き火が楽しめ、料理もできる火遊び道具の決定版。バーベキューにも!丈夫なステンレスボディとそれを4面から押さえる安定したスタンドは、重いダッチオーブンも載せられるほど強度十分で、安心して思う存分焚き火を楽しめます。直火では地面に残る焼け跡や芝生を傷めてしまうだけでなく焚き火の熱は地面の中の生物にとっても大敵です!地面との空間を十分とることが、ローインパクトな焚き火の絶対条件です。※本商品は直火によるフィールドへのダメージを防ぐことをコンセプトにしており、より多くの方にお使いいただけるよう、機能と価格のバランスを特に追求しています。炭火や焚…
¥ 7,500
2021-01-29 19:51
薪を置く部分が箱型になっており、その上に網を乗せるとBBQなどができるタイプです。
自作するには難易度が高いですが、金物の加工に慣れている人や道具を持っている人はぜひ挑戦してみてください。
次のページでは、焚き火台の作り方を紹介!