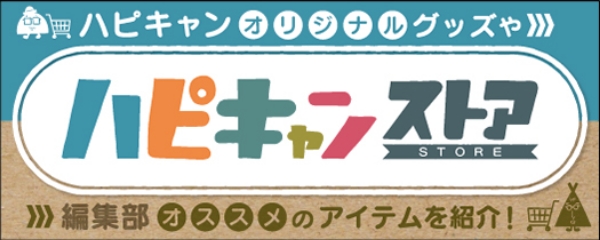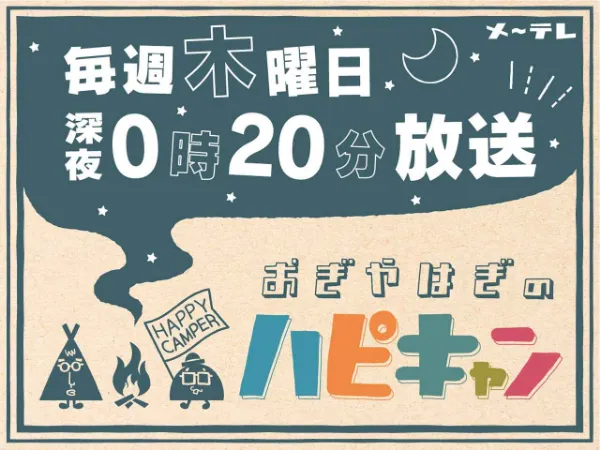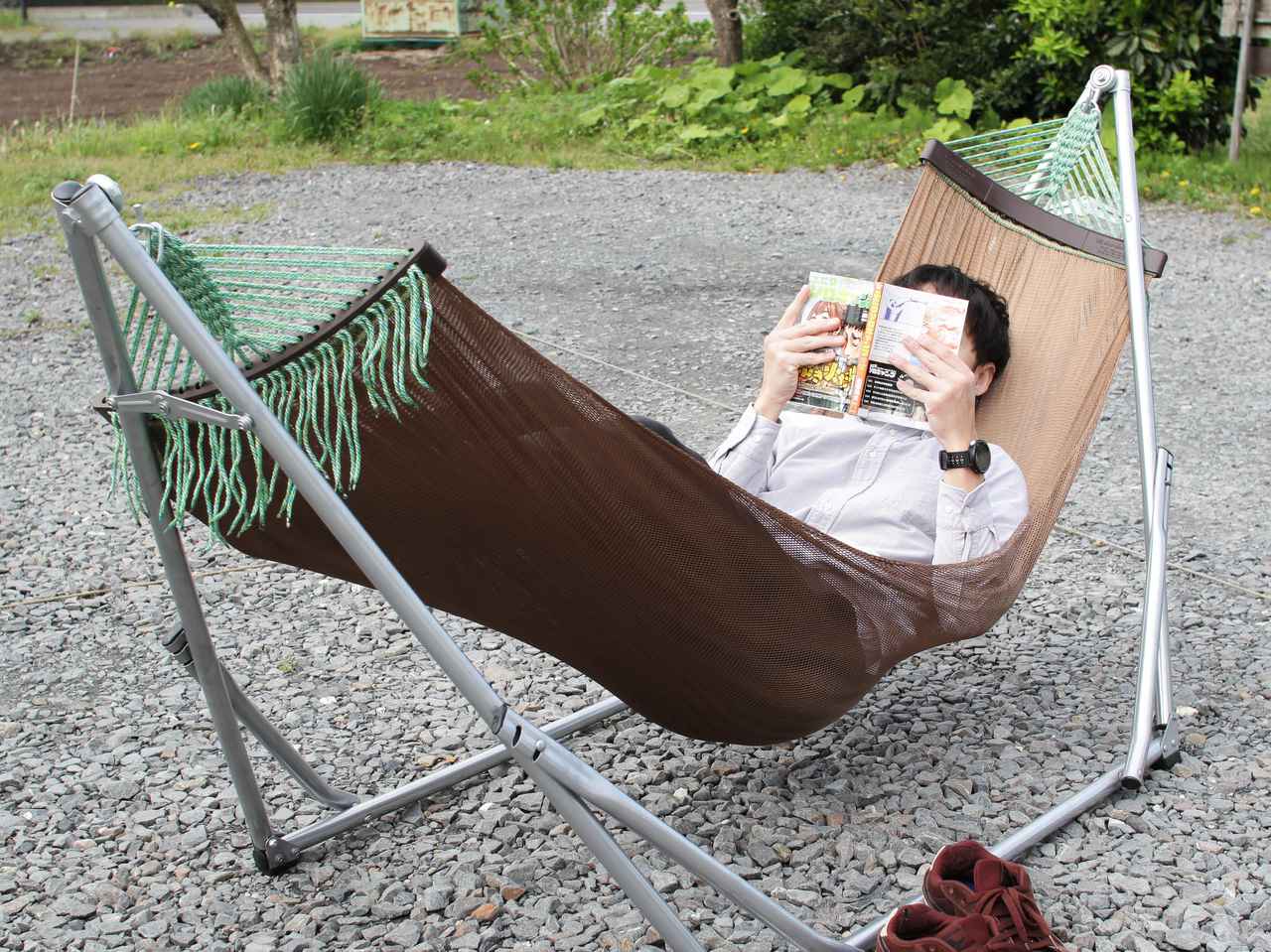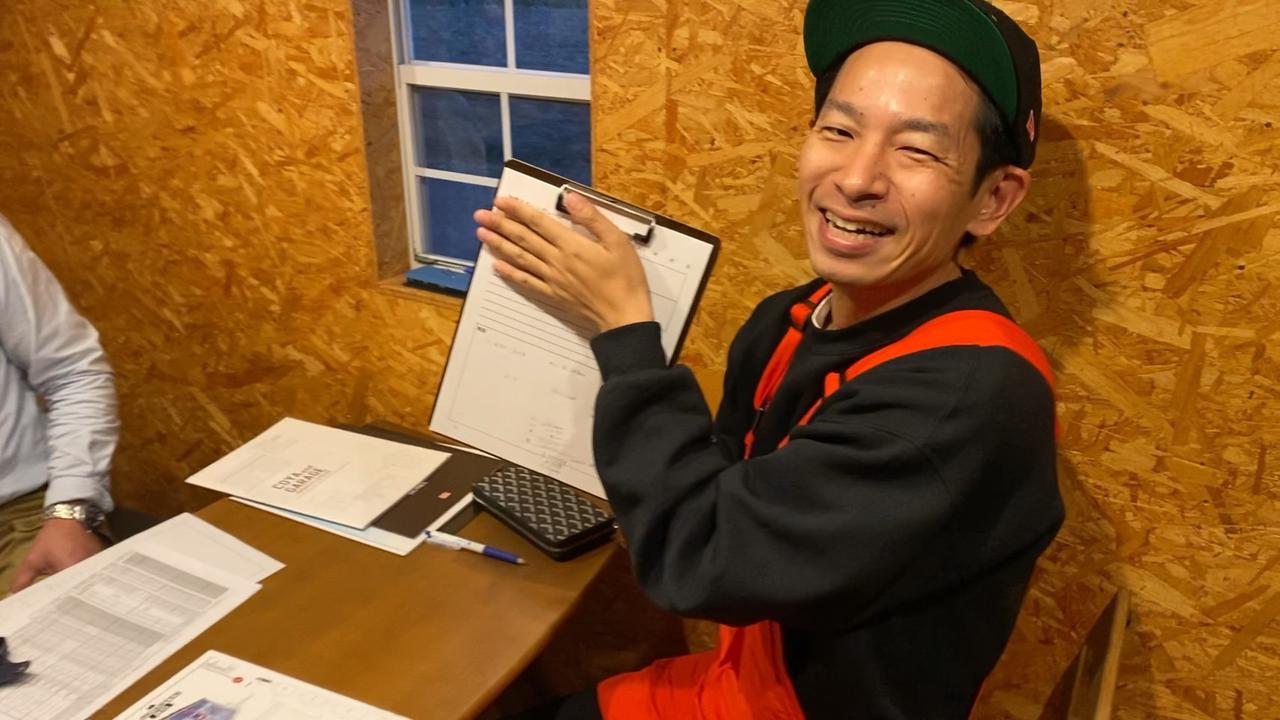【バケツ稲作り(春)】種まき前に「浸種」〜発芽後 苗床に種をまく〜葉が数枚出たら田植え
田んぼをイメージすると、初夏の時期の田植えや、秋の収穫を想像する人も多いかと思います。実際は、お米を育てる農家さんは春から田植え準備で大忙しです。
今回ご紹介する「バケツ稲で作るお米」も規模は小さいながらも「準備」や「育てる」という過程で気をつけるべきことはありますので、ポイント毎にご紹介していきたいと思います。
お米の場合、種をまく前の準備として芽を出す必要があります。お米の種から芽を出すためには、種を水につける「浸種」という作業が必要になってくるのです。

種から芽が出た様子
そして、種から芽が出てきたら「種まき」をします。
最初はバケツではなく、イチゴのパックや2Lペットボトルなどで作った容器に土を入れた苗床(なえどこ)に種をまきます。

種まきの様子
筆者撮影
そして数日すると葉が出てきます。

葉が伸びてきた様子
筆者撮影
苗が成長し、葉が3~4枚になったら、いよいよバケツに田植えをします。

田植えの様子
筆者撮影

田植え完了の様子
【バケツ稲作り(夏)】稲が生長したら「中干し」〜再度 水を張る〜お米の花が咲き受粉〜米粒が誕生
バケツの水を切らさないようにして、稲が40~50cmになってきたら、一度バケツの水を抜き、「中干し」という作業を行います。
中干しが完了したら、また水を張ります。

筆者撮影
稲にお米の花が咲きます。
おしべの花粉がめしべに付き、受粉が完了すると、もみの中にお米の粒ができてきます。

お米の花
【バケツ稲作り(秋)】穂が黄金色に変化したら稲刈り〜脱穀〜もみすり〜精米〜食べられるお米に!
穂ができて40~50日ごろ、穂が黄金色になってきたら稲を刈ります。
刈った稲はこのままでは食べられないので、穂からもみをとる「脱穀」といわれる作業を行い、もみすり、精米の作業をして、普段食べているお米の状態にしていきます。

穂が実った様子

脱穀の様子
春から秋の作業の流れをご紹介しました。
実際にお米を育ててみると、なかなか芽が出なかったり、苗の成長のスピードに驚かされたり、体験してみて、感じることもたくさんあります。
そのたびに「農家さんってすごいな!」という思いが湧いてきます。
2021年も無事、秋の収穫ができるよう、筆者も頑張って育てていきたいと思っています。