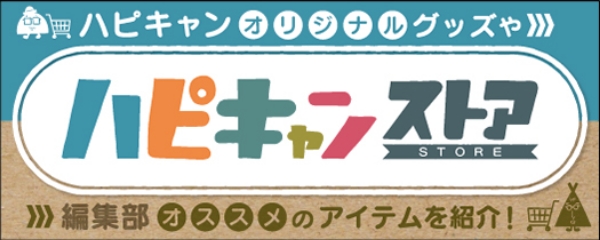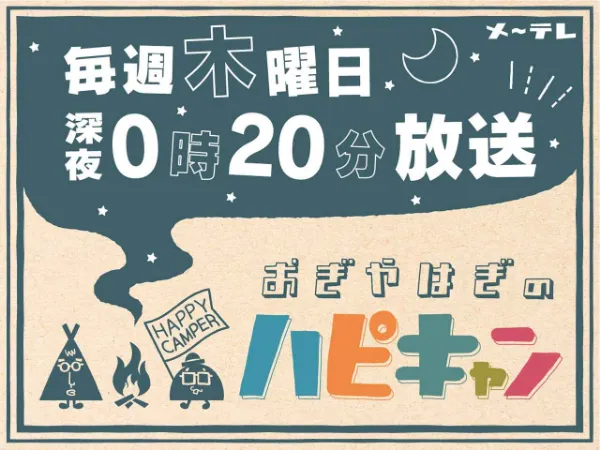キャンプ用語集
出典「知っておくと役に立つキャンプのことば」ソトレシピ編 ©SANSAIBOOKS 2022
あ行
あ
- アウトドアフェス
-
読み方 [ あうとどあふぇす ]
キャンプ場や大型イベントスペースなどを舞台とした、キャンプビギナーから筋金入りのキャンパーまで新たな楽しみを得られる屋外型イベント。アウトドアギアの販売、ミュージックライブ、体験型ワークショップなどを通じ、アウトドアやキャンプの魅力を体感できる。
- アクティビティ
-
読み方 [ あくてぃびてぃ ]
キャンプに付帯する、おもに体を動かして楽しむ「遊び」の総称。トレッキング、カヤック、SUP(スタンドアップパドルボード)、スノーシュー、フィッシングなどなど。近年は主目的をアクティビティとし、キャンプ場選びをベースキャンプとして考えるスタイルにも注目が集まる。
- 圧縮袋
-
読み方 [ あっしゅくぶくろ ]
寝袋など空気を多く含む道具の収納時、よりコンパクト化するためにベルトなどで圧縮する機能を備える袋。また別素材ではあるが、空気を抜くビニール製圧縮袋もキャンプの着替え用に利用すると持ち物をコンパクト化できて便利。100均ショップなどで手軽に手に入る。
- アプローチシューズ
-
読み方 [ あぷろーちしゅーず ]
もともとはクライミングの用途でトレイルを歩き、「岩場へアプローチ」するための便利な機能を備えるシューズ。摩擦力の高いアウトソールは適度なグリップ力を持ち、多少の悪路を歩くも安心。山歩きに対応する機能を持ち、コーディネートしやすいモデルも多くあるためキャンプとの相性はいい。
- アルコール
-
読み方 [ あるこーる ]
キャンプで使われる燃料のひとつ。エタノールやメタノールの混合成分で、おもに燃焼器具のアルコールストーブで使用する。薬局やホームセンターなどで「燃料用アルコール」として比較的安価で手に入り、旅先で見つけやすいことも魅力のひとつ。
- アルコールストーブ
-
読み方 [ あるこーるすとーぶ ]
アルコールを燃料とする燃焼器具で、略して「アルスト」。アルコールバーナーとも呼ぶ。市販モデルの素材はおもに真ちゅうやチタンで小型軽量。燃焼機構はとてもシンプルな構造なので、アルミ缶などを使用してDIYも容易である。燃焼時にはほとんど音がなく、日中は炎の目視がしづらい。調理時にはゴトクや風防も別途必要。
- アルミホイル
-
読み方 [ あるみほいる ]
BBQでのホイル焼きや蒸し焼き調理の蓋として活躍する他、丸めることで掃除アイテムとしても機能する。焼き網にこびりついた汚れを取ったり、クッカーの焦げ付きを削り落としたりする。キャンプやBBQ向きの「厚手のタイプ」もあり、熱に強く耐久性が高い。BBQグリルの火床全体に敷く用途に便利だ。BBQ後は灰ごと丸めて廃棄でき、かつグリルの汚れも最小限で済む。
- アンダーキルト
-
読み方 [ あんだーきると ]
ハンモックの下にセットする厚手の生地。地面から離れて浮く状況のハンモックには、下部に空気が対流しているため、気温が下がればシビアな対処法が求められる。理想はマットレスとアンダーキルトの併用。保温力を高めることでオールシーズン快適なハンモック泊ができる。
- R値
-
読み方 [ あーるち ]
マットレスの「断熱力」を表す数値。数値が低いと断熱力は低く、高ければ断熱力も高い。実使用による断熱の体感に個人差(男性・女性にもよる)はあるが、マットレス選びの参考値として重要な目安。ちなみにR値が1.5 と3 のマットレスを組み合わせた場合、単純に足し算で4.5 として考えられる。
い
- 一枚布
-
読み方 [ いちまいふ ]
ヘキサタープやスクエアタープなど、「一枚の布生地で構成されたタープ」のことを指す。
- 一酸化炭素中毒
-
読み方 [ いっさんかたんそちゅうどく ]
テントやシェルターなど密閉空間で燃焼器具を使用することで発生する、人体に有毒な一酸化炭素。初期に体へ及ぼす影響は頭痛やめまいなど風邪の症状と似通っている。においがないため、異変に気づかずそのままにしておくと一酸化炭素が充満して意識を失い、最悪の場合は死に至る恐ろしい事態に。冬場のキャンプでストーブなどを使う場合は一酸化炭素を検知する「一酸化炭素チェッカー」を常備したい。
- インタープリター
-
読み方 [ いんたーぷりたー ]
地域における植生や動物の生態、歴史や文化的背景に精通し、各地でのエコツアーや自然学校などで訪れたゲストに対し、自然からのメッセージを伝える案内人を指す。国家資格や認定制度ではない。
- インナーシーツ
-
読み方 [ いんなーしーつ ]
寝袋の内側に入れ込み、おもに保温性を高めるアイテム。素材はシルク、化繊など多彩で、いずれも吸湿速乾性を備える。感染症対策として宿泊施設のベッドや布団用に使用するのもあり。薄手のためコンパクトに持ち運べる。
- インナーシート
-
読み方 [ いんなーしーと ]
おもに「ファミリー向け大型テント内」の床面全面に敷くシートで、テント内を歩き回りやすい環境にする快適装備。地面からの熱や冷気が直接伝わるのを防ぐ役割も。クッション性を備えるものもあるが、それでも薄手。就寝時はこの上にマットレスを敷くことを推奨する。
- インナーテント
-
読み方 [ いんなーてんと ]
テントのダブルウォール構造における、フライシートの内側に設営する寝室部分のこと。フレームワークで自立する他、フライシートを設営したのち、その内側に吊り下げるタイプもある。また生地は3シーズン、4シーズン用に分かれる。
- インフレータブル
-
読み方 [ いんふれーたぶる ]
対クローズドセル空気で膨らませる方式のこと。キャンプの就寝時に使うマットレスや、カヤック、SUPなどに普及している。収納時にとてもコンパクトになり保管や車載がしやすい半面、セッティングや片付けには時間を要する。
- EDC
-
読み方 [ いーでぃーしー ]
EverydayCarry(エブリデイキャリー)、「いつも持ち運ぶ」道具の意味。コンパクトなバッグに必要最小限かつ最大限に活躍する道具を厳選し、それらをまとめて持ち運び、キャンプフィールドでスマートに使いこなす。以上を幾度も繰り返し、自分にベストのEDCを構築していく。ソロキャンプやブッシュクラフトのスタイルでよく取り入れられている。
う
- ウォータージャグ
-
読み方 [ うぉーたーじゃぐ ]
水を入れてキャンプサイトに配置。手洗い、料理用など、特にファミリーキャンプシーンでは使用頻度が高く、必須に近いアイテム。サイズ・素材はさまざまあり、人数に応じてセレクト可能。ソロやカップルキャンプでも、キャンプサイトから炊事場が遠いときには重宝する。
- ウルトラライト
-
読み方 [ うるとららいと ]
もとはアメリカで生まれたハイキングスタイルで「必要最小限の荷物で装備を極力軽くすることで移動時に体への負担が減り、楽に広範囲への行動が可能となる」という思想。派生して自転車ツーリングキャンプの他、ライトなソロキャンプでも応用して親しまれている。略して「UL(ユーエル)」とも呼ばれる。
え
- エコ洗剤
-
読み方 [ えこせんざい ]
植物由来の成分のみで生分解性が高く、自然に配慮した環境に負荷をかけない洗剤。キャンプにおいては、おもに炊事場での洗い物に使用する食器用洗剤を指す。キャンプ場によっては下水設備が都市部よりも整っていないことがあるため、常備しておきたい。
- エコツーリズム
-
読み方 [ えこつーりずむ ]
自然環境・歴史文化など、各地域固有の魅力を観光客に伝えることで、その価値や大切さなどが理解され保全につながっていくことを目指す仕組みのこと。それぞれがアクションすることで相乗効果を生み、豊かな自然を守りつつ活力を持続する、自然観光の理想形。
- エッグホルダー
-
読み方 [ えっぐほるだー ]
トレッキングやキャンプに、必要な分だけ卵を持ち運ぶためのアイテム。2個、4個、6個用などサイズは豊富で、内側には安全に運搬できる緩衝材が備わっている。
- エマージェンシーブランケット
-
読み方 [ えまーじぇんしーぶらんけっと ]
宇宙服の開発過程で生まれた超薄手の防寒用シート。畳んだ状態だと手のひらサイズだが、広げれば約2×1.3mまで広がる。金・銀の表裏構成で金側は熱を吸収し、銀側は熱を反射。寒いときには銀側を内側にしてくるまれば体熱を反射し保温効果を得られる。体を動かすたびにカシャカシャと音がして気になるが、これ一枚で非常に暖かい。
お
- おうちキャンプ
-
読み方 [ おうちきゃんぷ ]
自宅の部屋やベランダ、庭などで楽しむキャンプスタイルのこと。
- 小川張り
-
読み方 [ おがわばり ]
老舗ブランドogawaのシステムタープに付属する、セッティングテープによって生み出されるテントとタープの連結スタイル。これによりタープ下のスペースを最大限に活用できるメリットがある。
- 熾火
-
読み方 [ おきび ]
焚き火の薪、またはBBQの炭が、炎をあげていた状態から落ち着き、煙を上げず、赤い状態になっていること。それでも火力は安定し、遠赤外線効果で食材にじっくりと火を通す調理に最適な状態。
- オットマン
-
読み方 [ おっとまん ]
チェアに座って伸ばした脚を乗せ、浮かした状態で休むためのアイテム。キャンプ用としては携行しやすい折り畳みのスツールタイプが一般的。
- 温燻
-
読み方 [ おんくん ]
燻煙材に「スモークウッド」を使用する、スモーカーなどで食材を燻す手法のひとつ。スモークウッドに火をつけ、スモーカー内に配置して、50~80°Cほどで数時間食材を燻す。チーズやソーセージ、ちくわなどが手軽な温燻つまみとして人気。ウッドにしっかりと火がついていれば、初心者でも失敗なくできる。
- OD缶
-
読み方 [ おーでぃーかん ]
アウトドア仕様のガスカートリッジのことで、ODはOUTDOORの略。容量は110、250、500gで、ガスはイソブタン、プロパン、ノルマルブタンのいずれかが配合されている(配合比率は製品により異なる)。CB缶と比べると頑丈な構造なので内圧が上がりやすいプロパンを多く配合可能。寒冷地キャンプで火力が下がりにくい製品が多い。
- オートサイト
-
読み方 [ おーとさいと ]
テントやタープ、キッチン、焚き火スペースなどをセットしたスペースのすぐ横に、車を駐車してキャンプができる場所を指す。区画サイトやフリーサイトに分類される。オートキャンプ場とはオートサイトを備えるキャンプ場のこと。オートサイトは千差万別。眺望、日陰の有無、隣接サイトとの距離感、地面の固さ、広さなどえきれないほどのパターンの違いがある。車をサイトに横付けできるから設営・撤収時の労力が少なく、荷物が多いファミリーキャンパーには特に適している。
か行
か
- 加水分解
-
読み方 [ かすいぶんかい ]
「数年ぶりに使用するテントやタープなどの生地がベタついている.....」というのはよくある話。雨などで水分が加わることによりPU(ポリウレタン)コーティングが剥がれる現象のこと。例えばテントで加水分解が起きれば防水性が著しく低下し、雨天時には雨漏りをしてしまう。劣化を完全に防ぐことはできないが、対策としては「使用後には乾かし、汚れを取る」「保管場所は湿度が低いところを選ぶ」ことを徹底する。シューズのソールやレインウエアなどのジャケットも同様。
- 化繊
-
読み方 [ かせん ]
化学繊維の略。おもに寝袋やウエアの中綿保温素材として使用されている。ダウンと比較すると水濡れには強いが、保温力はやや劣る。収納状態も多少大きい。気軽に洗濯できるため、メンテナンスに気を遣わないで済む。
- 片落とし
-
読み方 [ かたおとし ]
ヘキサタープなどのオープンタープを設営する際、まずベーシックにメインポールで自立させる(ロースタイル仕様のため、ポールは通常よりも短めに設定する)。続いて片側の側面グロメット部分2カ所を地面にペグダウンし、壁状にして「片側を落とす」これを略して片落としという。もう一方の側面はサブポールやトレッキングポール、枝などでキャノピーのように張り出すことで、片落としスタイルのタープ設営は完了。
- カトラリー
-
読み方 [ かとらりー ]
食事で使用するスプーン、フォーク、ナイフ、箸などのこと。キャンプやアウトドア用に、素材はステンレスやチタン、木製まで多彩に揃う。
- カナディアンカヌー
-
読み方 [ かなでぃあんかぬー ]
キャンプ道具を満載し、湖や川を漕ぎ進む「キャンプ旅」に絶好のオープンデッキ艇。パドルは片側だけにブレードが付くシングルブレードを使用する。パドリングは「Jストローク」という、アルファベットのJを水中で描くような操作がベーシック。素材はポリエチレン、FRP、ロイヤレックス、ウッドなどさまざまで、基本は2人乗り艇。リジッド型の全長は14~16フィート(4.2~4.8m)が主流。サイズが大きいため、保管場所の確保が必要。不使用時には小さく畳んで保管できる、組み立て式のタイプもある。一方でカヤックはダブルブレードパドルを用いて漕ぐ艇。海での使用に適したシーカヤック、オールラウンドのシットオン、急流向きのシットインなど用途に応じてさまざまなタイプがある。近年人気のパックラフトもカヤックの部類で、とても軽量なインフレータブル式。その上コンパクトに持ち運びができるため、バックパッキングやバイクパッキングをしながらの川旅にも身軽に対応できる。
- かまど
-
読み方 [ かまど ]
火を熾し、焚き火をするスペースのこと。キャンプ場によっては野外炉(コンクリートやレンガ)が常設されている場合もある。直焚き火が可能なフィールドで、手頃な岩が複数あるのなら焚き火スペースを岩で囲うのがベーシック。適度な風除けになり、小物置きやトライポッドの吊るしなどにもフレキシブルに対応が可能である。岩などがなければ地面を掘る。焚き火と調理を効率的に同時進行するならば丸型穴を2つ用意する「キーホール(鍵穴)型」がおすすめ。焚き火用、煮炊き用の穴に分ければ調理もしやすい。
- カラビナ
-
読み方 [ からびな ]
開閉するパーツが付いた金属製のリング。もともとは登山用具として作られたもので、本格的なカラビナとなれば人の体重を支えるほど強度が高く、その分値段も張る。キャンプでちょこっとものを掛ける程度なら、強度が低く安価なタイプを選ぶとよいだろう。
- 空焼き
-
読み方 [ からやき ]
ガス、ホワイトガソリン、灯油などを燃料とする、燃焼式ランタンの光源「マントル」を燃やす作業のこと。すべて白くなれば作業は完了。空焼き後のマントルは衝撃に弱く脆いため触れないように注意。ターボ式のガストーチで行うと、火力の勢いで破けてしまうことがある。できれば風の影響がない状況の屋外で、ライターやマッチなどの炎を使って作業したい。この空焼きを行わないとマントルは美しく発光しない。
- 仮ペグ
-
読み方 [ かりぺぐ ]
タープを設営していて、風が強いときなど位置がズレないように「ひとまずペグダウンをする」こと。
- カンガルースタイル
-
読み方 [ かんがるーすたいる ]
親カンガルーの袋に子どもカンガルが入っている様子をイメージして名付けられた。おもにスクリーンタープやシェルターの中に小型テントを設営するスタイルのこと。秋、冬など寒い時季はカンガルースタイルのテントで泊まれば幾分暖かく眠れる。ちなみにオープンタープの下に小型テントを設営する場合も「カンガルー」とはイメージが離れてしまうが同義である。
- 完ソロ
-
読み方 [ かんそろ ]
ソロキャンプに出かけたキャンプ地で、他に誰もいないシチュエーションを指す。いわゆる「完全にひとりぼっち」の状態であること。
- 管理棟
-
読み方 [ かんりとう ]
キャンプ場の管理人がいるスペース。チェックイン、チェックアウトといった受付の他、売店を兼ねるところもあるなど、業態はキャンプ場によって違う。中心を意味する「センターハウス」と呼ばれることも多い。管理人は24時間常駐か、そうでない場合がある。
- カーサイドタープ
-
読み方 [ かーさいどたーぷ ]
タープの生地を車のルーフと接続し(グロメットに吸盤フックで固定)、車のサイドもしくは後方に張り出すタープのこと。開放感のあるオープンタイプや、シェルターのようにクローズできるタイプがある。いずれも車から離して自立させるには別途ポール、ガイロープ、ペグが必要。
き
- キッチンテーブル
-
読み方 [ きっちんてーぶる ]
スタンディングスタイルとロースタイルの2種類に大別される。基本には食材をカットするなどの作業台と、ツーバーナーを配置するスペースがセット。モデルによってはランタンポールや調理道具を吊るせるなど、作業しやすい設備が整っているものもある。スタンディングスタイルは天板の最低地上高が80cm程度あり、立った状態で調理するのに最適。
- キッチンレイアウト
-
読み方 [ きっちんれいあうと ]
キャンプ料理に力を入れるためには作業効率を重視。調理台とクーラーボックスやジャグなどの高さを揃えることや、調理時の動線をイメージするのが重要なポイント。クーラーボックスから食材を取り出す→ジャグの水で洗う(野菜)→カット・下ごしらえ→フライパンや鍋などをバーナーで熱するという流れを意識し、最適化を図る。ロースタイルキッチンは、座ったままですべてのポイントに手を伸ばしてアプローチできる「コックピット」のようなレイアウトが便利。家族や仲間とコミュニケーションを取りながら調理するなら、対面式キッチンのレイアウトがおすすめだ。
- キャノピー
-
読み方 [ きゃのぴー ]
おもにテントの前室側ドアパネルを張り出して作る「ひさし」のこと。キャノピーをセットするにはサブポール(コンパクトテントならトレッキングポールでも可)とガイロープが不可欠。またペグダウンで固定する場合はペグが必要となる。テントによっては後室や側面のドアパネルがキャノピーになるタイプもある。
- キャリーワゴン
-
読み方 [ きゃりーわごん ]
駐車スペースからキャンプサイトまで、キャンプ道具をまとめて運搬できるワゴン。多くは収束式フレームを採用しており、未使用時には細長く収納可能。ホイール径が大きく太いタイプを選ぶと悪路での走行に強い。ぬかるんだ草地の野外フェス会場などでも活躍。ワゴンの上に天板を配置すればテーブルとしても機能する。オートキャンプ場以外の野営場など、全国各地のキャンプ場を巡るのなら必須アイテムのひとつといえる。
- キャンステ
-
読み方 [ きゃんすて ]
愛車のウインドウや、クーラーボックスなどのキャンプ道具に貼る「キャンプステッカー」の略語。お気に入りのブランドやメーカーのキャンステはもちろん、自分だけのオリジナルキャンステを作成するキャンパーも多い。キャンプ場で名刺代わりの交流アイテムとしても活用できる。
- キャンパー
-
読み方 [ きゃんぱー ]
ひとりでも、カップルでも、ファミリーでも、キャンプを楽しむ人の総称。その他、キャンピングカーを略して呼ぶことも。【例】「ソロキャンパー」=ひとりでキャンプを楽しむ人。「軽キャンパー」=軽自動車ベースのキャンピングカー。
- キャンピングカー
-
読み方 [ きゃんぴんぐかー ]
関車中泊車の中にベッドやシンクなどを備えた、就寝可能な車の総称。ベース車両はさまざまで、トイレやシャワー、冷蔵庫などの設備は必ずしもすべてに備わっていない。軽自動車ベースの「軽キャンパー」、ワンボックスカーベースの「バンコンバージョン」あたりが普段使いでも取り回しやすいサイズ。トラックベース(キャブ付きのシャーシに架装)の「キャブコンバージョン」、マイクロバスベースの「バスコンバージョン」などは、中型タイプで快適性が高い。また、就寝スペースを牽引するタイプは「トレーラーハウス」と呼ばれる。トレーラーハウスはキャンプ場の宿泊施設として常設しているキャンプ場が多くある。
- キャンプエプロン
-
読み方 [ きゃんぷえぷろん ]
おもにキャンプでの機能性に優れたもので、設営・撤収、調理シーンなどで必要な小物をサッと取り出せる。アウトドアエプロンとも呼ばれる。ファッション性が高いものも多く、人気が高いアイテムのひとつ。ごくシンプルな前掛けタイプ、上半身もカバーするエプロンタイプ、さらにはベストタイプなど多彩に揃う。グローブやハンマーを収納できる大型のポケットを備えるものや、ボトルホルダー付き、はたまた薪運びができる仕様など、キャンプを快適にしてくれる機能や創意工夫のバリエーションは豊富。素材はコットン製が多く占め、いずれも耐久性は高いのが特徴。
- キンクラ
-
読み方 [ きんくら ]
薪を安全リングの中に通し、上からハンマーで薪を叩き割る画期的な薪割りギア「キンドリングクラッカー」の略称。2013年に産声を上げたキンクラは、ニュージーランドがルーツ。エーラ・ハッチンソン(当時13歳)が斧で焚き付けを作る母のケガを心配して考案し、特許も取得している。誰もが安全に、最小限の力で薪割りができるとあって今や世界中で愛用されている逸品だ。
く
- 区画サイト
-
読み方 [ くかくさいと ]
駐車スペースとテントやタープなどを設営するスペースがセットの、定められた区画のこと。設営する場所が明確に決まっているので、ビギナーがレイアウトするのにおすすめ。約10×10mが車とファミリー用テント&タープを余裕を持って設営できるサイズ感だが、キャンプ場によって区画サイズはさまざま。8×8mや、もっと小さいところもあるため区画サイズと自身のテントとタープの設営サイズは事前に照らし合わせる必要がある。隣接するサイトとの区切りは植え込みなどで明確な場所もあれば、ロープなどで簡素に作られた場所もある。高規格フィールドでは区画サイト内に専用の上下水道やトイレが設置してあることも。
- ククサ
-
読み方 [ くくさ ]
フィンランド北部・ラップランド地方が発祥の木製マグカップ。原料は白樺で、寒さの厳しい環境だからこそ生まれるそのコブ材をくりぬいてカップに仕上げている。ひとつひとつ熟練の職人が手作りをしていて、美しい木目は同じものはなく、どれを取ってもまさに世界にひとつだけのカップ。原料や作り方が異なる場合でもククサと称している製品があるが、正しくはククサ風のカップである。現地で作が異なる場合でもククサと称している製品があるが、正しくはククサ風のカップである。
- クッカー
-
読み方 [ くっかー ]
フライパンや鍋の他、ダッチオーブンやホットサンドメーカーに至るまで、火にかけて調理するアイテム全般をいう。キャンプ向きクッカーといえば一般的に携行性を考慮し軽量かつスタッキングができるものが基本。そして素材は熱伝導率の高いアルミ製が主流だ。アルミクッカーセットの中には、鍋やフライパンにフッ素樹脂コーティングを施したモデルもあり、焦げ付きにくくて手入れもしやすい。超軽量で耐久性の高いチタン製クッカーは近年、注目を集めているが、熱伝導率は低いのがデメリット。炒め物や炊飯は得意ではないため、湯沸かしに向くポットタイプが多い。
- クッキングウエア
-
読み方 [ くっきんぐうえあ ]
トング、レードル(おたま)、ターナー(フライ返し)、ナイフ、木べらといった調理用の器具全般。キャンプ向けにリリースされているアイテムもあるが、素材や機能は家庭用とほぼ同じものが多い。それゆえ、家庭用とキャンプ用の兼用はまったく問題なし。ただしキャンプに行く機会が多いのなら、キャンプ専用にクッキングウエアセットを常備するのがベター。不便なアウトドアでは調理時にクッキングウエアの定位置を決めておくことで、準備や片付けをスムーズに行える。
- クロスオーバー
-
読み方 [ くろすおーばー ]
異なる要素が互いの境界線を越えて交わること。【車両の例】クロスオーバーSUV=街乗り主体のベース車両ながら悪路までバランスよくカバーするオールマイティな走行性能を持つ。さらにはルックスもアウトドアテイストを醸しているモデルが多い。【アウトドアスタイルの例】クロスオーバースタイル=キャンプ、トレッキング、パックラフティングをミックスしてアウトドアを楽しむなど。
- クローズドセル
-
読み方 [ くろーずどせる ]
対インフレータブルマットレスの種類のひとつ。素材はおもにポリウレタンでマットの中に気泡膜が封じ込められている構造。ロール式と蛇腹式に分かれ、いずれにしてもセッティングや片付けのスピードはわずか数秒で済む手軽さ。マットによってはアルミ蒸着加工が施されており、アルミ面を体に接するように使えば熱反射で保温性が高まる。収納サイズは大きく、特にファミリーで人数分のマットレスを必要とするオートキャンプでは車載時のスペースを考慮する必要がある。
- クーラーボックス
-
読み方 [ くーらーぼっくす ]
大きくはハードタイプとソフトタイプに分かれる。ソフトタイプに比べるとハードタイプのほうが保冷力は高めのモデルが多い。保冷力の高さはおおむねボディの厚みに比例する。ハードタイプは場所を取るので、保管場所にはある程度余裕が必要。ソフトタイプは柔らかく、未使用時には半分以下の大きさに畳めるものもあるため、保管場所のスペースに不安がある場合は優先したいポイント。どちらかのタイプに絞るのではなく、例えばハードタイプの40ℓ&ソフトタイプの25ℓを併用するのもよいだろう。家族キャンプでは両方活用し、デイキャンプではソフトタイプだけなど、場面に応じて使い分けができる。
- クーラーボックススタンド
-
読み方 [ くーらーぼっくすすたんど ]
クーラーボックスを地熱の影響から守るため、またキャンプで利用しやすい高さを出すためのスタンド。クーラーボックス専用のロータイプや、ツーバーナーも配置できるハイスタンド、あるいはクーラーボックスにサイズの合うローテーブルやスツールを活用するのもいい。
け
- 携帯用浄水器
-
読み方 [ けいたいようじょうすいき ]
水道がないフィールドでも、川や湖の水を「安心して飲む」ためには必須のアイテム。一見、美しく見える透明な川の水でも細菌は多く存在するため、できれば浄水器を使って安全な飲料水を確保したい。実用的な携帯用浄水器は、持ち運びがしやすいコンパクトな「ボトルタイプ」と大容量の「ポンプタイプ」の2タイプがある。気になる細菌などの除去率はフィルターの性能によるため選ぶ際には細かく確認しよう。上下水道が整っているオートキャンプ場では必要としないが、手頃な価格のものもあるため、災害時のイザというときに備えて持っておくのもよいだろう。
- 結露
-
読み方 [ けつろ ]
キャンプではテントやタープ内、車中泊では車内に発生しやすい。室内と外気の気温差、人の呼気、湿度の高さなどアウトドアでの結露の発生要因は数多くある。カラッとした秋口あたりのテント泊では、結露が出ないこともあるが、それ以外の季節ではテント内に大抵は結露が出てしまう。テント内ではベンチレーションを開放。またダブルウォールテントでは、インナーテントとフライシートの間を開けてしっかりと設営をすることが大事。結露は完全に防ぐというより、空気の流れを意識してどれだけ抑止するかに注力しよう。
- ケトル
-
読み方 [ けとる ]
ヤカンのこと。キャンプ用には熱伝導がよいアルミタイプが多く、クッカーセットにスタッキングできるものもある。より軽量さを求めるならチタン製を、特徴的なカラーリングやビジュアルを求めるなら琺ほう瑯ろう製、焚き火と併用したいなら耐久性の高いステンレス製がおすすめ。また焚き火での使用を前提としたケトルには、吊るしやすいハンドルや、注ぎ口に灰が入らない蓋が付くなど、使う側に立った細かな配慮が施されている。
- ケビン
-
読み方 [ けびん ]
宿泊施設の呼び名のひとつで「キャビン」から派生。丸太ログ造りだったり、おしゃれな戸建てなど、設備についての明確な決まりはなく、キャンプ場によって形態はさまざま。トイレ、風呂・シャワー、寝具、キッチン、食器など貸別荘のように至れりつくせりの場合もあれば、雨風をしのぐための小屋といったシンプルなタイプもある(この場合、利用するには大半のキャンプ道具が必要)。宿泊施設を利用する際は利用料金だけではなく、設備についても事前に確認することが重要。
- ケロシン
-
読み方 [ けろしん ]
焚き火用途ならタフなステンレス製。持ち運び重視ならアルミ製やチタン製を選ぶ。〜ケロシン
こ
- コット
-
読み方 [ こっと ]
軍で使用されている組み立て式の簡易ベッド「G.I.コット」に由来。構造はそのままに、キャンプ向きの快適な仕様にブラッシュアップしている。生地にしっかりと張りが出てベッドのような弾力があることから、快眠を得られるアイテムとして人気が高い。タイプとしてはベンチとしても使用できる地上高の「ハイコット」と、限りなく地面に近い「ローコット」、そして可変式の脚フレームを採用したハイ・ローの切り替えができる「2WAYコット」の3種に分かれる。基本、生地は薄手の一枚タイプなので暑い時季の背面は涼しく快適。逆に寒い時季になると生地の下に対流する冷気が快眠の妨げになるので、それを解消するためにマットなどを敷くのが一般的である。荷物を置くスペースとしても便利。
- コッヘル
-
読み方 [ こっへる ]
ドイツ語が語源で、調理器具の意味。英語の「クッカー」とほぼ同じ意味なのだが、一般的には登山で使われる、アルミやチタン製の軽量・小型タイプについて呼ぶことが多い。つまりキャンプシーンに置き換えると、ダッチオーブン=コッヘルとはならないということ。
- コテージ
-
読み方 [ こてーじ ]
バンガローキャンプ場の宿泊施設としてポピュラーな部類で、コテージの名を冠した施設は、設備が充実していることが多い。おおむね寝具、家電、キッチン、トイレなど家庭に近い快適な設備が整い、食材以外は準備の必要がなくまさに「手ぶら」で泊まれるコテージもある。逆に、コテージという名前が付いている宿泊施設でも、設備が整っていないこともあるので事前に確認を。
- コンテナ
-
読み方 [ こんてな ]
ノコギリ、ナタ、ガストーチ、グローブなどの焚き火系アイテム、クッカー、ナイフ、ターナー、トングなどの調理系アイテム……といったふうに、キャンプの細かい荷物を用途別にジャンル分けして運ぶのはとても効率的だ。道具の定位置が決まると、キャンプ中も片付けの際も散らかることなく、極めて合理的といえる。そこで活躍するのがボックス形状のコンテナ。ひと昔前までは「オリコン」と呼ばれる折り畳み式コンテナが主流だったが、昨今ではポリプロピレン製の蓋付きトランクカーゴタイプやアルミタイプが台頭している。
- コンプレッションバッグ
-
読み方 [ こんぷれっしょんばっぐ ]
荷物を圧縮し、できる限りコンパクトにして持ち運べるようにするアイテム。圧縮するアイテムの代表格は寝袋で、モデルによってはその収納袋自体がコンプレッションバッグであることも。最も効果的なのは上下に蓋をするようなカバーが付き、3本程度のベルトで締め上げる構造。寝袋にもよるが、締め上げることで半分以下のサイズにシェイプすることも可能。登山やバックパッキングゴトク〜043でのソロキャンプに活用すれば、パック内の容量にそれだけ余裕ができる。
- コード引き込み口
-
読み方 [ こーどひきこみぐち ]
テント入り口のドアパネルの横や下にある幅10㎝程度のジッパー部分のこと。これにより家電の電源コードが通る最小限のスペースが確保される。秋・冬のキャンプで、電源付きキャンプサイトのテント内で家電(ホットカーペットなど)を使用する場合、コード引き込み口を使えば、人の出入りに干渉しないで済む。おもにファミリー向けのインナーテントに装備されている。
- コーナンラック
-
読み方 [ こーなんらっく ]
ホームセンターの「コーナン」が販売する折り畳み式の木製ラックのこと。タイプは2段、3段、4段があり、キャンプでは小物置きのスペースとして活躍する。折り畳むと薄く収納できるため、車載時は省スペースで済む実用性の高さが人気だ。シンプルなデザインはインテリアとしても溶け込みやすい。収納ラックやディスプレイラックとしての使い勝手もいい。ペイントを施して自分だけのオリジナルラックに変身させる楽しみもある。
さ行
さ
- サイト
-
読み方 [ さいと ]
キャンプをするスペースのこと。車の乗り入れが可能なサイトはオートサイトと呼び、定められた区画型のキャンプスペースは区画サイト、区切りがないサイトのことをフリーサイトという(車の乗り入れが可・不可の両パターンあり)。キャンプ場によって区画サイトだけのところもあれば、全面フリーサイトのところ、区画・フリーの両方から選べる場所もある。またペット同伴のキャンパーのために、専用のドッグランを併設したドッグサイトを備えているキャンプ場もある。
- サイトレイアウト
-
読み方 [ さいとれいあうと ]
キャンプをするスペースに、テント・タープ・車などの配置をレイアウトすること。特に初めて訪れるキャンプ場ならば、設営の前にスペースの状況を入念に確認したい。自分の使用できるスペースを見て、周囲の環境・隣接サイトとの距離、トイレや炊事棟までの距離、他のキャンパーが行き来するであろう動線、地面はどこがフラットで就寝スペースに適しているかなど、大事なポイントを整理したのち、どこにテント・タープを配置するのがベストかを検討する。実用的かつ快適に過ごせるレイアウトが想像できたら設営開始だ。何度か設営を経験するうちに養われるのは空間認識能力。自分のキャンプ道具のサイズ感とサイトのスペースを瞬時に照らし合わせ、どのように設営をすればよいのか、イメージできるようになるだろう。
- サイドオーニング
-
読み方 [ さいどおーにんぐ ]
キャンピングカーやバンのサイドから張り出せる、ロールタイプのシェードのこと。車のルーフサイドから直にセットアップできるため、設営・撤収時間を大幅に短縮できる。タープを設営しなくても、サイドオーニングが日差しや雨から身を守ってくれる。基本、キャンピングカーに装備されるものだが、後付けも可能だ。
- サウナテント
-
読み方 [ さうなてんと ]
キャンプとサウナは実に親和性が高い。サウナで「ととのったら」、すぐに自然の中に飛び出せるのだ。携行に優れたコンパクトなタイプのサウナテントが多数リリースされており、なかにはバックパッキングできるものもある。しかし一般に多いのはオートキャンプに持ち運び、設営するパターン。構造は至ってシンプルで、テントの中に薪ストーブを設置し、ストーブの上に載せた石(サウナストーン)に水をかけて水蒸気を発生させる。いわゆるセルフロウリュスタイル。川べりのキャンプ場はより好適地で、川が天然の水風呂となる(設営可能なフィールドか、事前に要確認)。キャンプ場によってはモバイルタイプを常設している場所もある。
- サコッシュ
-
読み方 [ さこっしゅ ]
語源はフランス語で、「カバン・袋」の意味を持つ。発祥はツール・ド・フランスに代表される自転車のロードレースで、ドリンクや補給食を入れるために使用されていた自転車用のショルダーバッグである。小型で軽量、薄型なのが特徴で、登山やキャンプではスマートフォン&財布といった最小限の荷物をスマートに持ち運べる。
- SUP
-
読み方 [ さっぷ ]
StandUpPaddleboard(スタンドアップパドルボード)の頭文字を取った略語。ハワイが発祥のパドルスポーツで、サーフボードに似ているが非なるもの。ボードの上に立ち上がり、シングルパドルを使って漕ぎ進むのがベーシックな乗り方だが、あぐらをかいても、寝転がっても、膝立ちで漕いでも、ヨガをしてもよし。シンプルな一枚板が功を奏し、楽しみ方は自由自在である。インフレータブル式(空気を注入する方式)と一枚板の2タイプに分かれるが、キャンプとの親和性が高く初心者向きなのはインフレータブル式。セッティングには多少労力がいるが、安定感に優れたモデルが多い。また折り畳むとコンパクトに収納できるため、車載しやすいし自宅での保管場所にもさほど困らない。使用後、洗って乾かすのも素早く済むため、メンテナンスの手間も少ない。海や川、湖など水辺のキャンプでは思いのほか気軽にSUPを楽しめる。
- サニタリー
-
読み方 [ さにたりー ]
キャンプ場にあるサニタリー棟とは、トイレ・炊事棟が集まっている施設を指す(場合によってシャワー・浴室も追加)。英語「Sanitary」をカナ表記にしたもので言葉の意味は、衛生的な、清潔な、など。キャパシティが大きめの高規格キャンプ場で見かけることが多い。
- サーキュレーター
-
読み方 [ さーきゅれーたー ]
酷暑のキャンプでは欠かせない送風機のこと。充電式バッテリー搭載のコンパクトなモデルが主流だ。テントやタープ内の空気循環を助ける使い道にも注目で、結露の抑止にも効果を発揮する。
し
- シェラカップ
-
読み方 [ しぇらかっぷ ]
アメリカの「シエラクラブ」という自然保護団体が発祥の金属製の持ち手付きカップで、キャンプの必需品とシーム〜047いっても過言ではない万能アイテム。飲み物を飲むカップ、フライパンや鍋代わりの調理器具、汁物をよそうおたま、食事の際の取り皿など、活躍の場は実に多彩だ。チタン、ステンレス、真ちゅう、さらには樹脂製など素材もさまざま。ベーシックな容量は330㎖だが、50㎖や500㎖のタイプもある。同容量で同形状のシェラカップ同士なら省スペースにスタッキングできるため、持ち運びもしやすい。
- シェルター
-
読み方 [ しぇるたー ]
タープの部類ではあるが、イメージとしては一枚布タープに側面のパネルを追加し、居住空間を生地で覆うことができるアイテム。英語の「Shelter」をカナ表記したものであり、そもそもは避難するスペースのことを指し示す。ブッシュクラフトで設営する居住スペースのこともシェルターと呼ぶ。
- シェード
-
読み方 [ しぇーど ]
公園でのピクニックや浜辺でのリラックススペースなどに最適なコンパクトなタイプ、収束式フレームなどで脚部を自立させて雨・風・日差しを防ぐ大型のタープタイプなど、さまざまなタイプのひさしのこと。大型タイプはサイドウォールなどを追加して機能を拡張できるモデルもあるが、基本は「日除け」としての役割が一番大きい。
- 鹿番長
-
読み方 [ しかばんちょう ]
アウトドアギアブランド「キャプテンスタッグ」の別称。ロゴに使用されている鹿が語源で、キャプテンスタッグの道具を愛するキャンパーにより命名。ユーザー間による非公式な呼び名だったが、2017年、キャプテンスタッグから正式に公式キャラクター「鹿番長」がデビュー。同社の人気モデルである折り畳み式のアルミ背付ベンチは「鹿ベンチ」と呼ばれ親しまれている。
- シダープレート
-
読み方 [ しだーぷれーと ]
アメリカ生まれのBBQ「ウッドプランク」を楽しむための一枚板(おもにスギ材)のこと。水やお酒でよく濡らしたシダープレートの上に好みの食材を載せて、グリルで熱して焼き上げる。食材に香りが付き、簡単にスモーク調理ができる。シダープレートのままテーブルに出せるメリットもある。
- 島キャンプ
-
読み方 [ しまきゃんぷ ]
日本には多くの離島があり、キャンプができる島も数えきれないほど存在する。東京から行くなら船でアクセスできる島として伊豆七島の島々が最も身近である。島旅をする上で、身軽さを重視するならバックパッキングだろう。本格登山ほどパッキングにシビアにならなくてもいいが、軽く、コンパクトにできればもちろん移動は快適。島での最適な移動手段は、訪れた島の規模にもよるが、レンタカー、レンタサイクル、レンタルバイクなど。燃焼器具の燃料には注意が必要で、飛行機移動の場合はガス缶の運搬ができないため、現地での調達がマスト。小さな島ではOD缶が手に入らないことがあるので事前に島で手に入る燃料をチェックし、最適な燃焼器具を持参すること。
- 車中泊
-
読み方 [ しゃちゅうはく ]
関キャンピングカー車に宿泊する旅のスタイル。ミニバンやワンボックスが主流と思われがちだが、どんな車でも可能で、ソロなら軽自動車やコンパクトカーでも大丈夫。最も重要なポイントは寝心地だ。ベッドメイキングはシートを倒してフラットに近づける手法が一般的だが、車種によっては後席シートを前方に倒したほうがフラットになることもある。凸凹の解消には時間と手間を要するため最適な方法をまずは確かめたい。次に押さえるポイントはプライバシーの確保。外から車内が丸見えというのは視線が気になっていただけない。また車内に明かりが差し込んだ状態では落ち着いて眠れない。就寝時には簡易的なカーテンやサンシェードで目隠しを準備しよう。なお、就寝時にエンジンのかけっぱなしはNG。環境に悪影響を及ぼすし、周囲のキャンパーに騒音などの迷惑もかかるので注意が必要だ。
- シュラフカバー
-
読み方 [ しゅらふかばー ]
シュラフ(寝袋)の外側をスッポリと覆うカバーのこと。素材には防水透湿性に優れるゴアテックスなどが採用され、2層構造(表地・防水透湿メンブレン)と3層構造(表地・防水透湿メンブレン・裏地)の2タイプが主流。おもな役割としては寝袋のパフォーマンスアップ。シュラフカバーを装着することで空気の層が増え、保温性が向上する。内側から発生する汗の水蒸気を外側に逃がす一方で、外気に触れるシュラフカバーの外側を結露などによる水濡れから守ってくれる。自身の持つシュラフの快適温度域では不安な寒い地域に出かける場合に重宝するだろう。
- ショックコード
-
読み方 [ しょっくこーど ]
テントやタープ、組み立て式のチェアなどのポールの中に入っているゴム紐のこと。このショックコードがあるおかげでポールがバラバラにならず、広げると連結しやすい仕組みになっている。使い続けるうちにゴムが伸びてしまい設営・撤収がしにくくなる。応急処置としてはショックコードを短く切って結び直す手法があるが、いずれまた伸びてしまうことを考えると、丸ごと交換するのがおすすめだ。
- ショルダーウォーマー
-
読み方 [ しょるだーうぉーまー ]
おもにマミー型寝袋の内側の肩口に配されたチューブ状の部分のこと。ジッパーをしっかりと閉じることで肩口からの冷気の侵入を防ぎ、保温性を高める役割を持つ。
- シングルウォール
-
読み方 [ しんぐるうぉーる ]
関ダブルウォールダブルウォールテントならフライシートとインナーテントの2層構造だが、シングルウォールとはテントの就寝スペースが生地一枚だけのこと。高性能な防水透湿素材が使われ、軽量で1~2名用のモデルが主流。なかには1kgを切るタイプもある。フライシートがない分、設営・撤収の時間を短縮できる。荷物を極力減らして軽量化をしたい山行やバックパッキングといったシチュエーションにおすすめ。
- シングルキルト
-
読み方 [ しんぐるきると ]
寝袋の縫製法で、表地と裏地を直接「つぶし縫い」した構造のこと。縫い目によってロフト(かさ)がなくなるため、そこがコールドスポットとなるが、中綿の偏りがなく、軽量でコンパクトに収まる。中綿は化繊のタイプが多く、春~夏向きの寝袋に適している。
- シンデレラフィット
-
読み方 [ しんでれらふぃっと ]
他社のギアを組み合わせてみたらまさかのジャストフィット!というような事象のこと。メスティンの中にアルコールストーブ、風防、燃料、カトラリーなどをピタリと収めたり、異なるメーカーの鍋とフライパンがぴったりハマったりと、意外にも相性がいい組み合わせを見つけると気持ちいい。
- CB缶
-
読み方 [ しーびーかん ]
CassetteGasBombeを略して呼んだガスカートリッジのこと。家庭用のカセットコンロでも扱え、手に入れやすい燃料である。容量は250gが一般的だが、より小型の120gタイプもある。ガスはイソブタン、プロパン、ノルマルブタンのいずれかが配合されている(配合比率は製品により異なる)。OD缶と比べると構造上の強度は低いためプロパンの配合率は劣る。そのため寒い場所では充分なパフォーマンスを得られないことがある。
- シーム
-
読み方 [ しーむ ]
関防水レインウエアなどの防水素材の機能性ウエアに使用されている防水テープのこと。テントやタープといったキャンプの幕体の縫い目に沿って圧着されている。使い続けていると劣化して剥がれてくることがあり、シームテープが機能しなくなると、そこから雨漏りが発生してしまう。シームテープは単体で販売されているため、自分でアイロンを使っての貼り替えも可能。ギアの寿命を延ばすには早めの交換が賢明だ。
す
- 炊事棟
-
読み方 [ すいじとう ]
キャンプ場の中で上下水道があり、作業台など炊事の作業ができるスペースを完備している施設のこと。屋根付きであることが条件で、屋外、屋内どちらのパターンも該当。キャンプ場によっては温水が出る蛇口を設置しているところもあり、寒い時季でも快適に食器洗いができる。高規格のフィールドでは冷暖房完備の屋内型炊事棟もある。
- スカート
-
読み方 [ すかーと ]
4シーズン向きのテントやスクリーンタープ、シェルターの裾に付く生地。きれいに接地させることで密閉度が高まり、外気が幕内に入らず保温性を高めてくれる。泥除けの「マッドスカート」も同じ役割。
- スクリーンタープ
-
読み方 [ すくりーんたーぷ ]
屋根と側面のドアパネルをフルクローズできるタープのこと。床面はフロアレスで、おもな用途はリビングスペース。多くのモデルはドアパネルをメッシュにしながら通気性を確保したタイプで、虫除けの効果もある。夏場にはドアパネルをフルメッシュにし、コットで就寝すれば涼しく快適だ。一枚布タープに比べると開放感は劣るが、フルクローズにすれば悪天候時でも安心してスクリーンタープ内で過ごすことができる。
- スタッキング
-
読み方 [ すたっきんぐ ]
クッカーやシェラカップなどを重ねてコンパクトにまとめること。キャンプ道具の特徴のひとつとして挙げられるのがこのスタッキング。上手にスタッキングができれば、道具の運搬、準備、収納がスムーズになり、よりキャンプが快適に。
- スタッフサック
-
読み方 [ すたっふさっく ]
バックパックの中で小分けに使用する収納袋のこと。サイズは大小さまざまあるため、大きなスタッフサックはオートキャンプでも活躍する。防水性に優れるもの(ドライサック)もあり、濡れた衣類やウォーターアクティビティ用のギア入れなどにも使える。
- ステルス張り
-
読み方 [ すてるすばり ]
一枚布のタープをステルス戦闘機のようなスタイルに設営すること。設営にはスクエア形状でループが多数付いているタープが適している。必要なポールは1本(ポールの先端にはタープ生地を保護するタオルなどの当て布が必要)。ソロキャンプの場合、3×3mサイズのタープをステルス張りすることで快適なスペースを確保できる。
- ストライカー
-
読み方 [ すとらいかー ]
関メタルマッチ焚き火やバーナーの着火に使用する火熾しアイテムで、ファイヤースターター、メタルマッチのマグネシウム(フェロセリウム)ロッド(棒状部分)に擦り火花を散らせて対象物に着火する。ライターなどを使用せず、麻紐をほぐした火口に着火する場合は、まずストライカーでロッドのマグネシウムを削って粉を火口に載せる。そして火花を散らすと火口に着火し、勢いよく燃える。
- スノーシューズ
-
読み方 [ すのーしゅーず ]
雪道でも滑りにくいソールを持ち、高い保温性と防水性を持つ冬用シューズのこと。スノーブーツとも呼ぶ。スノーシューなどで雪深いエリアを歩く場合にはハイカットモデルがベストで、シューズ内への雪の侵入を防ぐことができる。
- スパッタシート
-
読み方 [ すぱったしーと ]
焚き火台を使って焚き火をする際、地面にこぼれ落ちる熱い薪の塊などから地面を守る役割のシートのことをいう。もとは溶接作業時に出る火花を受けるシートで、素材には耐炎化繊維が採用され、生地が燃えることはない。芝のサイトやウッドデッキの上など、焦がす危険性がある場所で焚き火台を使う場合にはマストアイテム。スパッタシートを敷いておくことで、焚き火周りの後片付けが楽になるメリットもある。
- スポーク
-
読み方 [ すぽーく ]
フォークとスプーンが一体化しているカトラリーで、軽量&コンパクトな形状が魅力。スプーンの先に小さなフォークが付いたタイプ(おもにチタン製)と、持ち手を中心にしてスプーンとフォークがそれぞれ反対側に付いているタイプ(おもに樹脂製)の2パターンが挙げられる。後者はフォークのサイドにナイフが実装されているものが多い。
- 炭
-
読み方 [ すみ ]
大きく分けると「黒炭」「オガ炭」「成型炭」「白炭」の4つ。「黒炭」は着火しやすく高火力を発揮するキャンプ向きの炭で、ホームセンターや100均ショップなどでも目にする最も一般的なタイプ。国産の高品質なものなら火保ちがよいが、安価なものだとすぐになくなってしまう。「オガ炭」は木材を加工する際に出たオガクズを再利用した炭のこと。圧縮加熱成型され、チクワのような形状が特徴だ。火保ちがよく、コストパフォーマンスもいいので、キャンプにはおすすめ。「成型炭」は、オガ炭と原料は似ているが、圧縮加工成型した上に着火剤を塗った炭のこと。取り扱いブランドによっては、廃棄されるヤシガラを再利用したものもある。着火剤が練り込まれているので容易に火がつき、瞬く間に炭全体に火が回って熾火になる。最速でBBQを始められるタイプの炭で火力は強く、持続力もあるが、分量に対して価格は割高。保管期間が長いと湿気るため、着火にはガストーチがあると万全である。「白炭」はいわゆる備長炭で、火力の安定性はダントツだが他の炭に比べ圧倒的に着火に時間がかかるのがデメリット。キャンプというよりは業務用向きの炭といえる。
- スモーカー
-
読み方 [ すもーかー ]
食材を燻製するために使用する道具。温燻に対応するものでは「段ボール」のボックスタイプがエントリーモデルとしておすすめ。他に温燻・熱燻に対応する「金属製(鉄・ステンレスなど)」のボックスタイプ(円柱形状)のものもある。バーナーなどの熱源を使用する熱燻対応としては「陶器製」や「金属製(鉄・ステンレスなど)」がある。
- スモークウッド、スモークチップ
-
読み方 [ すもーくうっど、すもーくちっぷ ]
「スモークウッド」はおもに温燻で使用。木材を粉状にして固めたもので、さくら、なら、ヒッコリーなどの樹種から食材に応じてセレクト可能。着火させたのち、炎を落ち着かせてから火のついた部分が熾火の状態になれば準備はOK。ウッドから煙が上がり、その煙で食材に香り付けができる。固形タイプだが柔らかく崩れやすい。「スモークチップ」はおもに熱燻で使用。木材を細かく砕いてチップ状にしたもので、香り付けに選べる樹種はおおむねスモークウッドと同じ。スモーカーやクッカーにチップを敷き、バーナーなどの熱源でチップが熱せられて煙が発生する。基本的に直接火をつけては使わない。
- スリーシーズン
-
読み方 [ すりーしーずん ]
「春」、「夏」、「秋」3つの季節を示し、この時季に適したアウトドア製品をセレクトする際の目安の用語。目立って使われるのはテントで、3シーズン対応タイプはメッシュのインナーテントを採用し、通気性のよさを前面に押し出している。寝袋やマットレスでは対応温度域を知る目安にもなる。
- スリーピングバッグ
-
読み方 [ すりーぴんぐばっぐ ]
寝袋、シュラフ(ドイツ語:Schlaf)いずれも同義語。形状は大きく封筒型(「レクタングラー型」も同義)とマミー型の2つに分類される。封筒型はゆったりとした作りで布団のように眠れる半面、マミー型と比較すると保温力は低い。また肩口が広く開いているためそこから冷気の侵入を許してしまう。ジッパーを開いて広げての使い道もあり、敷布団や掛け布団としてもよし、同型を2つジッパーで連結すれば親子で就寝も可能。収納状態はマミー型よりも大きいため、オートキャンパーに向いている。マミー型は使用時にミイラ(Mummy)のようなフォルムになることからそう呼ばれる。体に密着して無駄なく保温してくれるだけでなく、封筒型よりもコンパクトに収納できる。寝袋から変化して、手足を出して自由に動かせる「着る」寝袋もある。いずれの型でも中綿には化繊とダウンがあり、どちらを採用しているかによって保温性や収納性は変わる。
- スリーブ
-
読み方 [ すりーぶ ]
テント、スクリーンタープ、シェルターなどに配された、ポールを通す部分のこと。インナーテントを設営するときなどは、自立させるために最初にポールをここに通す。またスクリーンタープではキャノピーを張るためのスリーブもある。スリーブはスムーズな設営をサポートする目的もあり、メッシュ地のスリーブは引っ掛かりが少なく設営がしやすい。
せ
- 雪中キャンプ
-
読み方 [ せっちゅうきゃんぷ ]
雪の中で行うキャンプのこと。春~秋のキャンプよりも圧倒的に装備が多く、暖かく快適に過ごすための経験値も必要なので、ビギナーにはハードルが高い。設営時は周囲の雪を踏み固めることから始まり、寒さの中でのテント設営はスピーディさが求められる。初めて雪中キャンプに挑戦するのなら、ホットカーペットなどの家電で暖まれるAC電源付きのオートサイトがおすすめ。さらには温泉が併設されているなど、快適に過ごせる施設が充実しているかどうかも選ぶポイントだ。雪や結露によってテントが濡れることは避けられないため、帰宅後に乾燥させる必要がある。雪中キャンプとは以上のような手間や労力がかかり大変だが、思わぬ感動や楽しさを得られるのもまた、雪のおかげなのである。
- セッティングテープ
-
読み方 [ せってぃんぐてーぷ ]
小川張りで、タープを設営する際に使用するアイテム。テントとタープを連結する際、タープ下の有効活用面積を最大限広く使うために役立つアイテム。使用法は、セッティングテープの片側をタープ生地のグロメットもしくはテープのループに固定し、もう片側をタープポールまで伸ばす(長さは任意で設定)。そのポールを自立させれば小川張りの役割を果たせる。
そ
- ソロキャンプ
-
読み方 [ そろきゃんぷ ]
ひとりで出かけるキャンプスタイル。またそれを楽しむ人のことを「ソロキャンパー」と呼ぶ。性別や年齢にかかわらず、確たるスタイルはなく、日光がソーラーパネルにバッチリ照射される天気なら、短時間でモバイル機器を充電できるモデルは数多い。
- ソーラーパネル
-
読み方 [ そーらーぱねる ]
キャンプで実用的なのは、おもに折り畳み式で広げて太陽光を一度に多く吸収できる携帯タイプ。USBポートが付いているため、モバイル機器・LEDランタンなどを直接充電できる。ポータブル電源と互換性があるモデルであれば、家庭用電源がなくても太陽光からの蓄電が可能。
た行
た
- 耐水圧
-
読み方 [ たいすいあつ ]
生地に染み込もうとする水の力を抑える性能値。対応数値の目安は「小雨・500㎜」「普通の雨・1
- 耐熱テーブル
-
読み方 [ たいねつてーぶる ]
おもにステンレス製の天板を採用したテーブル。熱したダッチオーブンを載せたり、焚き火台を載せて焚き火をしたり、分離式のワンバーナーを使用したりと、燃焼系アイテムと併用しても安心なテーブルのこと。ファミリーキャンプではサイドテーブルの役割を持つような小型のものが多いが、ソロキャンプならメインテーブルとして使えたり、クーラーボックススタンドとして活用したりなど汎用性が高まる。
- 耐熱・防火シート
-
読み方 [ たいねつ・ぼうかしーと ]
焚き火やBBQなどをする際に地面を保護する目的で敷くシート。ガラス繊維やカーボンフェルトなどの素材でできており、耐火性に優れる。サイズはさまざまあり、スパッタシートと組み合わせて使用するとより安心。
- 焚き付け
-
読み方 [ たきつけ ]
薪に確実に着火するためのきっかけを作る、燃えやすい材のこと。自然素材の場合、松ぼっくりやスギの葉(油分を含む)、細い枯れ枝などを利用するが、よく乾燥していることが前提だ。家庭で手に入るものは牛乳パックやガムテープ(布タイプ)、また裏ワザとしてはポテトチップスも焚き付けに利用可能だ。
- 焚き火台
-
読み方 [ たきびだい ]
火床を地面から離した状態で焚き火をするための金属製の台。ひとり用のコンパクトなサイズからファミリー対応のモデルまでサイズは幅広い。用途に応じて素材・形状は多種多彩に揃う。焚き火から地面を保護する役割の他、焚き火料理が作りやすかったり、オプションアイテムを追加して使い道を拡張したり、片付けも楽にできたりとメリットが多い。焚き火台は、キャンプで焚き火を楽しむ上での必需品といっても過言ではない。耐久性の高いステンレスの火床を使用しているモデルが大半だが、軽量性を謳ったチタン製のモデルも見受けられる。
- 焚き火ハンガー
-
読み方 [ たきびはんがー ]
焚き火スペースのそばに配置する重厚な鉄製ハンガーのこと。ハンガーの軸となる棒を地面に直接打ち込み、焼き網やツールハンガーをセットする。焚き火で作業や調理をする際、火ばさみなどのツールは地面に置いて見失いがちだが、ハンガーがあればそんな不安は解消。焚き火道具の居場所が決まる。
- タープ
-
読み方 [ たーぷ ]
ヘキサ型、スクエア型、ウイング型など、一枚布で作られた屋根のこと。ファミリー向けとして一般的なのはヘキサ型(ヘキサゴン:六角形)で、比較的屋根下の面積を広く確保できる形状。家族でもゆったり使いたい場合やグループには、スクエア型(四角形)が対応しやすい。スクエア型で屋根下の空間を有効活用するには、四隅に高さを出すための4本のサブポールが必須。またスクエア型にはループが複数付いたタイプもあり、ブッシュクラフトスタイルのような応用設営を得意とする。ウイング型はベーシックなひし形のタイプなら、張り綱を伸ばしてペグダウンするポイントが少ないため設営は手軽。ただし、日陰となるエリアが狭いため少人数に対応するモデルが多い。イレギュラーで八角形のウイングタープもあるが、その場合は屋根下が広くファミリーでの使用に向いている。素材は軽量なナイロンのバックパッキング向きなものから、コットンやポリコットンを採用したヘビーなモデルまで多彩に揃っている。
ち
- チェア
-
読み方 [ ちぇあ ]
チェアは座面の高さを基準として、「ハイスタイル」「ロースタイル」「グラウンドスタイル」と大きく3つのカテゴリに分かれる。選ぶポイントは3つあり、まず1つ目は「座面」について。座面に張りがなく、座ると沈み込むような「リラックスタイプ」は上半身が後傾しやすく、逆に前傾姿勢をとりにくい。座りながらのテーブル作業や食事には不向きだ。対して座面がピンと張っている「オールラウンドタイプ」は背筋を伸ばした姿勢をキープしやすい。2つ目のポイントは「背もたれ」。背もたれが長いモデルは「ハイバック」と呼ばれ、背中を預ける範囲が広いため長時間座っても快適に過ごせる。背面生地が多いため収納は大きくなるが、リビングでのんびり過ごしたい人にはおすすめだ。3つ目のポイントは「構造」。脚フレームを収束して細長く収納できる「収束タイプ」はかさばらず、車載もしやすい。パタンと畳める「折り畳みタイプ」は手軽に扱えるが、持ち運ぶには多少かさばるのが難点だ。複数台を車載する場合は工夫が必要だ。ヘリノックスチェアに代表される「組み立て式」は最もコンパクトに持ち運べるタイプで、小型のモデルなら車載時に荷物の隙間を見つけて押し込める。
- 地産地消
-
読み方 [ ちさんちしょう ]
出かけた地域の食材を仕入れて、その土地で消費すること。例えば道の駅で販売している野菜は、新鮮なものが比較的安く手に入る。また生産者が運営する直売所では、ちょっと不揃いなものがより安価で購入できるだけでなく、生産者の顔も見えるので安心。キャンパーにとってメリットが多い。継続的に利用者がいることで生産者の収益増加も期待できる。
- チャコスタ
-
読み方 [ ちゃこすた ]
ユニフレームがリリースするロングセラーモデルの名称で、チャコールスターターの略。煙突効果を利用した折り畳み式の簡易火熾し器で、BBQの炭や焚き火の薪を素早く着火できる優れもの。使い方はとても簡単でチャコスタ内に適当な量の炭や薪を入れ(空気の通り道を作るため、ぎっしり入れない)、チャコスタの外に置いた着火剤に火をつける。その上にチャコスタを置くと、短い時間で着火できる。
- 着火剤
-
読み方 [ ちゃっかざい ]
BBQの炭や薪を素早く着火させるためのアイテム。大きく「固形」と「液体」BBQの炭や薪を素早く着火させるためのアイテム。大きく「固形」と「液体」のタイプに分かれる。固形は主成分にパラフィンワックスを使用したものや、粉状にした木材を固めてそこに灯油を染み込ませたもの、オガクズを固めたものなどがある。小分けにして利用でき、燃焼時の継ぎ足しに使っても問題なし。「液体タイプ」はジェル状の着火剤で、主成分にはメチルアルコールが含まれている。必要な分量を調節でき、火力は固形よりも強い。なお、絶対にやってはいけないのが燃焼時の継ぎ足し。液体タイプは非常に可燃性が高いため、燃焼している薪に継ぎ足しすると炎が瞬時に着火剤に伝って大惨事になる恐れがある。取り扱いには充分に注意を。
- チャークロス
-
読み方 [ ちゃーくろす ]
着火剤の役割を果たす、炭化させた綿100%の布のこと。チャークロスの作り方は至って簡単。用意するものは「100%コットンの布(着なくなったTシャツなどでもOK)」「蓋付きのスチール缶(100均ショップで購入可)」「金属性ペグ、ハンマー」「燃焼器具(焚き火台orバーナー)」。作り方:1.10㎝四方に布をカット。適当でよし。2.カットした布を缶に入れたのち、缶の蓋にペグで穴を開ける。3.缶を火にかける。次第に蓋の穴から煙が出てくるのでそのままに。4.煙が止まったら先ほど使用したペグで穴を塞ぎ冷めるまで放置。冷めたら蓋を開け、布が真っ黒になっていれば完成。チャークロスとは、いうなればBBQなどで使う炭の超小型版。小さな火花から着火する際に重宝する。
つ
- ツェルト
-
読み方 [ つぇると ]
山行や源流釣行などでやむなくビバークするときなど、風雨から身を守るための緊急用テント。生地はシングルウォーが基本で、トレッキングポールや立木の幹などを利用して簡易的に設営する。一般的なツェルトは緊急時の使用が第一で、軽さと持ち運びやすさを優先している。そのため就寝時の広さや過ごしやすさ、さらには防水性などの機能面ではテントよりも劣るものが多い。
- 吊り下げ式
-
読み方 [ つりさげしき ]
インナーテントの構造のひとつ。フライーシートを先に設営したのち、その内側にあるフレーム、もしくは生地内側のループにインナーテントを吊り下げて固定するタイプのこと。コンパクトテントから大型のシェルターまで、吊り下げ式を採用しているモデルは多岐にわたる。メリットは雨天時でも濡れずにインナーテントを設営・撤収できることと、インンナーを取り付けずにシェルターとして活用できること。デメリットは、結露が多いときなどは乾かすのに時間がかかること(取り外しに多少時間がかかり、かつインナーテントも単体で自立しないため)。この問題を解決したのがフライシートとインナーテントが一体化したまま設営&撤収が可能な簡易設計モデル(ワンタッチ式など)だ。
- ツールハンガー
-
読み方 [ つーるはんがー ]
おもにショックコードで連結されているポールをつなげて組み立てる軽量タイプ(主素材はアルミ)で、キャンプ道具を吊るしたり引っ掛けたりするハンガーラックのこと。サイズは大小ありスタイルに応じて選択可能。コンパクトに持ち運べるが、耐荷重は高くないため、吊るしたりするアイテムは軽量物を対象にしている。用途は似通っているが、鉄製の熱に強い焚き火ハンガーとは別モノ。足しに使っても問題なし。
て
- 鉄板
-
読み方 [ てっぱん ]
熱伝導がよく、蓄熱性が高い鉄板は、食材を美味しく焼き上げてくれる上、シンプルな調理法を可能にするため、古くから人気の高いアイテムだ。BBQグリルに付属しているような鉄板もよいが、最近では厚手のタイプに人気が集中している。ソロキャンプブームの影響もあり、ワンバーナーのゴトク上で使用できるコンパクトなソロ向きのサイズも増加傾向にある。フラットタイプや縁が立ち上がっているタイプ、厚さが3㎜程度から極厚の8㎜など、好みで選べるといった具合だ。メスティンやラージメスティンにスタッキングできるものもある。
- テンション
-
読み方 [ てんしょん ]
タープやテントを設営する際に使用。張り綱をピンと張ること、生地がピンと張った状態を指す。タープの設営では、最後の仕上げにすべての張り綱の自在を調節してしっかりとテンションをかけることが大事。
- テント
-
読み方 [ てんと ]
「モノポール型」は1本のポールで自立するタイプでごくシンプルな形状なので、設営に迷うことはない。構造上、側面が上に向かって収束しているためデッドスペースが多い。「ドーム型」は2本のフレームをクロスして湾曲させて、インナーテントを自立させるタイプ。設営の手軽さと室内空間の広さを両立しており、ビギナーにおすすめだ。「ツールーム型」は、寝室とリビングスペースが一体化しているタイプ。別途タープを設営しなくても、居住性の高いリビング空間を作り出せ、サイトレイアウトを細かく考える必要がない。「トンネル型(カマボコ型)」は非自立式で筒状のシンプルな構造。吊り下げ式の寝室を備えたツールームタイプが主流。「エアフレーム型」はエアポンプで膨らませるタイプで、極太のフレームの強度は抜群。「ロッジ型」はスチール製ポールを採用した直線基調で、居住性の高さが一番の魅力。「パップテント型」は軍幕・ソロキャンプブームにより近年新たに追加されたタイプで、開口部が広いロースタイルが主流。
- テント・タープの生地素材
-
読み方 [ てんと・たーぷのきじそざい ]
ノルディスクに代表される、「コットン」を100%使用したテント・タープは、グランピング施設でも人気。コットンは吸湿性に優れ、結露の発生を軽減してくれる他、繊維内に空気の層ができるため外気の侵入を防いでくれる。そのためテント内は暑い時季は涼しく、寒い時季は暖かい。加えて耐火性も非常に高い天然素材である。ポリコットン素材(コットンとポリエステル混紡生地。TCとも呼ぶ)のテントやタープをリリースするブランドも急速に拡大。前述のコットンの特徴をそのままに、軽量で乾きやすいポリエステルがミックスされていて、風合いや使用感は限りなくコットンに近い。コットンとポリコットンに関してはどちらも水を含むと乾かすのに時間がかかってしまう点と重量がある点がデメリット。そして、最も採用されている生地素材が「ポリエステル」。耐久性があり、吸湿性が低いので濡れても乾きやすいのが特徴。紫外線による劣化にも強い。近年は酷暑の影響もあり、太陽光を90%以上カットする遮光生地を採用するテントやタープが増えてきた。真夏の日差しにテントが照らされてもテント内は日差しの影響を受けず、涼しく快適だ。テントの素材表記に見る「D(デニール)」とは、糸の太さを示しており数値が大きいほど厚い。つまり75Dなら細く繊細な生地で、150Dならより太く丈夫な生地ということになる。
- テント・タープのポール素材
-
読み方 [ てんと・たーぷのぽーるそざい ]
FRP(グラスファイバー)ポールは安価なタイプ。よくしなるがアルミポールに比べると重く、負荷をかけすぎたり、劣化が進行すると割れてしまう。エントリーモデルのテントによく使用されている。アルミ合金は強度と弾性に優れ、スチールに比べてしなやかなため曲線を多用するドーム型やトンネル型テントに使用されることが多い。ジュラルミンもアルミ合金の一種である。スチールは重量があり、しなりが少ない。一部ロッジ型テントを愛するキャンパーから親しみを込めて「鉄骨」と表現される素材。直線的な使用で性能を発揮し、ロッジ型テントやスクリーンタープで多用されている。他にはテントのキャノピーポールやタープのポールとしても使われている。
- テーブルの天板
-
読み方 [ てーぶるのてんし ]
キャンプのリビングや焚き火周りなど、サイトで快適に過ごすには欠かせないテーブル。選ぶポイントとして注目したいのが天板素材である。樹脂製天板の場合は拭き取り掃除がしやすく、軽量なため持ち運びもしやすい。熱には強くないので熱いものを載せるなら鍋敷などが必須だ。木製タイプの天板はナチュラルな雰囲気が自然環境によく合って使いやすいものばかり。ショックコードの入ったロール式の他、細い板をラダー状に配置した天板&折り畳み式脚タイプ、一枚板天板&折り畳み式脚タイプなどがある。アルミ天板は、その多くがショックコード入りのロール式を採用しており、とにかく軽量でコンパクトに持ち運べる特徴がある。その他、焚き火台を設置できるステンレス製の耐熱天板を採用したモデルも人気だ。
- テープ
-
読み方 [ てーぷ ]
タープの四隅にあるグロメットの先や、ファミリーテントのインナーテント下部の四隅などに付くナイロン製のループ(輪)のこと。頑丈なパーツで、タープの設営時にはこのテープに張り綱を通して引っ張る。前述のインナーテント下部にあるテープは、ペグダウンをしてテントを固定する重要な役割を担う。
と
- 灯油ストーブ
-
読み方 [ とうゆすとーぶ ]
薪ストーブと人気を二分する、冬キャンプのヌクヌク暖房器具。灯油ストーブのいいところは燃料代がリーズナブルで、とにかく手軽なこと。1泊2日のキャンプだったら自宅で燃料タンクを満タンにしておけば充分足りるし、電源がないサイトを利用する場合でも灯油ストーブで暖かく過ごせる。気をつけたいのは一酸化炭素が発生する燃焼器具のため、テントやスクリーンタープ内で使うにはリスクが伴うこと。万が一に備えて一酸化炭素チェッカーとの併用がおすすめだ。
- トラッシュボックス
-
読み方 [ とらっしゅぼっくす ]
ゴミ箱のこと。キャンプでの主流は筒状のポップアップタイプで、本体を広げたら筒の中にビニール袋を広げて固定するだけ。スーパーやコンビニのビニール袋をそのままサイトのゴミ入れとして使うと、風で飛びやすいし開口部はクシャクシャになってゴミを入れにくい。何より美しくない。トラッシュボックスがあるとキャンプサイトは清潔感が保たれ、複数あればゴミの分別も楽に行える。
- トレイルランニング
-
読み方 [ とれいるらんにんぐ ]
登山道や林道など、未舗装路を中心に自然環境の中を走り抜けるスポーツ。略して「トレラン」と呼ばれる。ハードに山岳を走るイメージから「山岳レース」とも称される。距離に応じてクラス分けされていて、基本は長距離。24㎞までのXXSクラスから、210㎞以上のXXLクラスまで用意。シューズは、競技に向いたグリップ力が高いトレイルランニングシューズを使用。このシューズは脱ぎ履きしやすいローカットが一般的で、悪路に強い特徴があり、キャンプ用のシューズとしても適している。キャンプと登山を併せて楽しむにはぴったり。
- トレッキングポール
-
読み方 [ とれっきんぐぽーる ]
おもに登山で歩行をサポートするポール。適切に使用することで脚への負担は著しく軽減される。収納法には「折り畳み式」と「伸縮式」があり、折り畳み式はテントのショックコード入りポールと同じ構造で、細かな長さの調節はできないため、アップダウンのある地形で使いこなすのは難しい。オールラウンドなのは伸縮式で、上りと下りで適した長さに調節ができる。荷物を極力少なくしたいキャンプスタイルなら、トレッキングポールをメインポールとして使えるテントを併用したい。またコンパクトタープのポールとして使ってもよいだろう。
な行
な
- ナイフ
-
読み方 [ ないふ ]
ナイフのおもな種類はハンドルと刃が固定されている「シースナイフ」と、刃をハンドルに収納できる「フォールディングナイフ」。それ以外に近年人気が高いのは、ブッシュクラフトで使われるブッシュクラフトナイフ。なかでも代表的なのはスウェーデンのブランド・モーラナイフで、その汎用性の高さからメジャーな存在として知られる。枝を加工するなどの細かい作業や、薪を割るバトニング、食材をカットする作業もストレスなくこなすことができ、オールマイティ。フォールディングタイプの代表格といえばオピネル。携行しやすいコンパクトなモデルは、お守り代わりに持っておくと安心だ。ナイフのおもなグラインド(断面)の種類は、研ぎやすく一般的な「フラット」、切れ味のいい内側にえぐれた「ホロー」、両側に膨らんだ「コンベックス(ハマグリ刃)」が挙げられる。また刃先の形状もさまざまあり、万能タイプの「ユーティリティポイント」、切る・皮をはぐことが得意な「ドロップポイント」、刺したり細かい作業向きの「クリップポイント」などが代表的。
- 中綿
-
読み方 [ なかわた ]
寝袋やダウンジャケットなどに使用される保温材のこと。一般的には化繊素材のものが中綿にあたるが、ダウンも中綿として含まれることが多い。ダウンは復元力が高く少量でも保温力に優れるが、水濡れに弱いというデメリットもある。ダウンはデリケートなため、洗濯時はダウン専用の洗剤を使うのが好ましい。洗濯後は自然乾燥の場合、ダウンの偏りを防ぐため平らな場所に干す。劣化を防ぐため日陰干しが推奨されており、気温が低い場合は完全に乾くまで時間がかかる。手間を省くなら、コインランドリーなどで乾燥機を使うのがおすすめ。化繊はダウンよりもかさが増え、収納状態は大きめ。価格はリーズナブルでメンテナンスが容易なため、洗濯機で日常的に洗濯が可能だ。
に
- 二次燃焼
-
読み方 [ にじねんしょう ]
焚き火台、ネイチャーストーブ、薪ストーブ、ロケットストーブなど燃焼器具に関わる、燃焼の仕組み。燃焼した際に発生した煙(可燃ガス)に再度高温の空気が当たることで2度目の燃焼が起きること。二次燃焼になれば煙が排出される量は格段に減り、高火力が持続。また燃やし切ると灰も少なくて済むなどメリットが多い。半面、燃焼スピードが速く薪の消費量も増えるのがデメリットといえる。
- ニトスキ
-
読み方 [ にとすき ]
ホームセンター・ニトリで販売されている鋳鉄製スキレットの総称。1~2名用に適した15㎝(6インチ)、2~4名に対応する19㎝(8インチ)の2サイズ展開。リーズナブルな上、家庭でもキャンプでも手軽に扱えるシンプルなスキレットだ。使い始めはシーズニング(ダッチオーブンの項で説明)が必要。
ね
- ネイチャークラフト
-
読み方 [ ねいちゃーくらふと ]
木の実や落ち葉など、身近な自然素材を使って日用小物を作ること。キャンプ場のワークショップや自然学校のプログラムなどで行われている。もちろん、オリジナルで自由に行うもよし。木の実と枝でデコレーションしたフォトフレーム、どんぐりと落ち葉で作った動物のオブジェなど、まずは手軽なところから始めたい。
- ネイチャーストーブ
-
読み方 [ ねいちゃーすとーぶ ]
枯れ枝や松ぼっくりなどの自然素材を使って火を熾し、燃焼させた炎で調理ができる道具。一枚板のシンプルなタイプ、二次燃焼をする筒状のタイプがある。ほとんどのネイチャーストーブは焚き火の用途の他、アルコールストーブや固形燃料の風防兼ゴトクとしての機能も持っている。
- ネイチャーツーリズム
-
読み方 [ ねいちゃーつーりずむ ]
自然のあるエリアに訪れる旅全般を指す。キャンプはもちろん、ホテルなどに宿泊しても、自然の中に身を置き、楽しむことがネイチャーツーリズム。ツアーに関しては厳格な定義があるわけではなく、自然保護の観点が疎かだったりすることも。例えば「ネイチャーツアー」という名が付いていても、自然から得る学びがあるとは限らない。
- 熱燻
-
読み方 [ ねっくん ]
燻煙材にスモークチップ使う燻煙法のひとつ。80℃から150℃の高温で食材を燻し、加熱調理とほのかな香り付けを同時進行する手法。温燻に比べると30分~1時間程度と燻煙時間は短い。スモーカーの下部にチップを敷き詰め、バーナーなどの熱源により加熱。熱せられたチップから煙が発生し、スモーカー内の食材は高温で燻される。豚バラや鶏モモ肉など油脂が多く出る食材を熱燻する場合は、チップに油脂が落ちないようにアルミホイルでカバーを作るとよいだろう。
- 燃焼式ランタン
-
読み方 [ ねんしょうしきらんたん ]
光源のマントルを燃焼・発光させるタイプとしては、ホワイトガソリン式(コールマン:ワンマントルランタンなど)、灯油式(ペトロマックス:HK500など)、ガス式(OD缶・CB缶タイプなど多数)があり、これらのおもな特性は、リビングやキッチンなどの広範囲を明るく照らせること。できる限り地面から離すことでその効果を充分に享受できる。大型で大光量のタイプは必然的に本体も大きく重量もあるため、安定感のあるランタンスタンドが必要となる。ちなみにキャンドルランタンも燃焼式ランタンに含まれる。いずれもテントやシェルターの室内では、一酸化炭素中毒などの恐れがあるため使用不可。
の
- ノコギリ
-
読み方 [ のこぎり ]
おもに焚き火用の薪や枝を切り分けるときに使用。キャンプに向いているのは、木工用の大きなものではなく、持ち運びしやすいもの。具体的には、刃を折り畳めるフォールディングタイプがおすすめだ。ワイヤーが刃の役割を持つ手のひらサイズのワイヤーソーもある。
- ノット
-
読み方 [ のっと ]
張り綱やパラシュートコードなどで結ぶ結び目のこと。例えば「もやい結び」を英訳すると、ボーライン・ノット(Bowlineknot)という。結び目によってはヒッチと呼ぶものもあり、「自在結び」はトートライン・ヒッチ(Taut-linehitch)という。
は行
は
- ハイスタンド
-
読み方 [ はいすたんど ]
収束式の脚フレームを採用したハイスタイル対応のスタンド。おもにキッチンでツーバーナーやクーラーボックスを安定して置く役割を担う。
- 灰捨て場
-
読み方 [ はいすてば ]
焚き火やBBQで出た使用後の灰を捨てられる場所。消火されていない状態で捨て場に放り込むと、火災の恐れがある。完全に火が消えたことを確認してから処理を行うこと。また薪の燃え残りが多く、灰捨て場のスペースを大きく使ってしまうような場合には、そのまま捨てず、まずキャンプ場のスタッフに適切な処理法を確認したい。
- 白灯油
-
読み方 [ はくとうゆ ]
灯油、ケロシン、白灯油とあるが、実際はどれも同じ。ホームセンターなどでの購入時に気をつけたいのは、ホワイトガソリン(→P.108)と間違えないこと。同じ液体燃料だが、使用する器具が違うので注意したい。
- 撥水
-
読み方 [ はっすい ]
テント、タープ、ウエアなど、生地の外側に加工を施して水をはじくこと。撥水性を保ったり、復活させたりするアイテムとしてスプレータイプと塗るタイプ(スポンジなどで塗る)がある。どちらのタイプもテントやタープを設営した状態で塗布作業を行うと効率がいい。スプレータイプを塗布する場合は、周囲のキャンパーに迷惑にならないよう、風向きなどに注意したい。
- ハブ構造
-
読み方 [ はぶこうぞう ]
テント、組み立て式のテーブル、チェア、コットなどのフレームの継ぎ目に使われる構造で、中心地点や中継地点の意味を持つ「Hub」に由来している。ハブとなるパーツを基準とし、そこから多方向へフレームを伸ばすことで複雑なフレームワークがスムーズになり、セッティング、片付けの高効率化が実現。ハブ構造のテントは居住性の高い空間を生み出しやすい。
- 張り綱
-
読み方 [ はりづな ]
テント、タープなどを固定するための綱。一般的にテントやタープを購入すると必要な本数の張り綱が同梱されており、設営時に張り具合を楽に調節できる自在金具(樹脂の場合もあり)も付属する。ガイライン、ガイロープとも呼ばれる。
- ハンギングチェーン
-
読み方 [ はんぎんぐちぇーん ]
キャンプ向きに作られた、小物を吊るすループ付きのベルト。シェラカップやヘッドランプなどを吊るすのにとても便利なアイテム。タープの下はもちろん、車ではアシストグリップを使って天井のスペースを有効活用するなど活躍の場は多彩。デッドスペースをうまく使える実用性の高さと、おしゃれな機能美を両立させた製品と言える
- 飯盒
-
読み方 [ はんごう ]
軍隊で使われているクッカーセット。一般的には本体、蓋、中皿で構成され、素材はおもにアルミ製。形は兵式、丸型が多く、アウトドアメーカーが販売しているモデルも見受けられる。日本のキャンプシーンでは米を炊くことを主目的に使用されているが、ベテランキャンパーは取り皿やフライパンとしても使用する。また炊飯と同時に蒸し野菜を調理すれば、米に圧を加えてふっくら美味しく炊き上げることができるなど、すこぶる機能的。ひと昔前なら焚き火で米を炊くという固定観念にとらわれがちなアイテムだったが、多様化する現代のキャンプスタイルにおいて汎用性の高さから人気が上昇している。メスティンも飯盒の一種。
- ハンドアックス
-
読み方 [ はんどあっくす ]
携帯に便利なコンパクトな斧。キャンプではナタの使い方とほぼ同じく、用途は薪割り。片手で振りおろす
- ハンドライト
-
読み方 [ はんどらいと ]
懐中電灯タイプの携帯式ライトのこと。ハンディライト、フラッシュライトとも呼ぶ。おもな光源はLEDで、キーホルダーとして使える超小型のものから全長30㎝以上のものまでサイズはさまざま。軍や警備などプロの現場で使用されることを想定したモデルが多く、キャンプ向きのヘッドランプと比較して最高照度はどれもみな明るい。バッテリー内蔵タイプなら、モバイルバッテリーとしても使えるものもある。ヘッドが可動するL字形のタイプならバックパックのショルダーに固定することが可能。夜間の行動時にはヘッドランプと同じような使い方ができる。
- ハンモック
-
読み方 [ はんもっく ]
2本の支柱(樹)の間に吊り下げ式の生地を設置して就寝するアイテム。中南米が発祥とされる。日常的に扱いやすくオートキャンプでも適したコットン素材や、バックパッキングできる超軽量なナイロン素材がある。どちらも背面に空気が対流するため涼しく、揺らぎの中で心地よくリラックスできる。宿泊に特化したハンモックは数多く、エアマットを背面にセットすることでフラットになったり、虫の侵入を防ぎながら通気性を確保するメッシュ付きのタイプもある。また自宅での使用や木々のないオートキャンプ場でも使用できるタイプとして、自立式のスタンドを組み立て、その間にハンモックを設置する方式がある。テントを持たず、冬場にハンモック泊でキャンプをする場合はハンモックの外側にアンダーキルトをセットし、さらに背面にマットレスを敷けば冷気対策は万全。これを知っておけば、オールシーズン、ハンモックライフを楽しめる。
ひ
- 火育
-
読み方 [ ひいく ]
都会での生活を送っていると火に触れる機会はとても少なく、オール電化の家庭なら皆無といっていいだろう。火育とは、火を扱うことでその利便性や危険性を学ぶこと。キャンプで子どもに実践するにはうってつけ(現代では、大人にも当てはまる)。火熾しの不便さや大変さから始まり、火力をコントロールして焚き火料理を作るなど、キャンプをする流れの中で楽しく正しい扱い方を学び、身につけるのが理想。災害時の備えとしても注目されている。
- 火消し壺
-
読み方 [ ひけしつぼ ]
火がついたままの炭を入れたのち、蓋を閉めて消火する壺。消火した炭は次回以降のキャンプでも再利用できるため、効率よく燃料を使い切れるエコな道具。消火してすぐは壺が熱くなっているため、近くにいる人(特に子ども)には注意を促すこと。サイトから灰捨て場が遠い場合の灰処理にも使え、手間が省ける。
- 非自立式
-
読み方 [ ひじりつしき ]
テント本体にペグダウンをしないと自立しない構造のテントに使われる言葉。おもな非自立式テントといえば、ワンポール型、トンネル(カマボコ)型が挙げられる。
- 火床
-
読み方 [ ひどこ ]
焚き火やBBQをする際、炭や薪を配置して燃焼させる場所のこと。焚き火台の火床は空気の流れを促すため、本体の最下部から少し浮いた部分にロストル(網状もしくは穴あき状のプレート)を配置している。焚き火台と似た構造だが、BBQグリルでは「炭床」と呼ばれることもある。
- 火ばさみ
-
読み方 [ ひばさみ ]
焚き火では薪、BBQでは炭をつかむために使うトングのことを指す。熱いものをつかむため、柄の部分は長めの設計になっている。うっかり地面に置いてしまうことが多く、踏みつけてしまいがちなので注意が必要だ。焚き火ハンガーやツールハンガーがあれば予防できるし、何より実用的。
- 100スキ
-
読み方 [ ひゃくすき ]
100円均一ショップで購入できる鋳鉄製スキレットの総称。ショップで購入できる価格は、実際のところ200円+消費税も含まれるが、100スキと呼ばれている。丸型とスクエア型のコンパクトなタイプが多数揃っている。丸型は直径約15㎝で、対応人数は1~2名向きである。家庭のキッチンでも日常的に扱いやすく、ソロキャンプではワンプレート調理をするのにいい。使い始めにはシーズニングをする必要がある。
- ヒーターアタッチメント
-
読み方 [ ひーたーあたっちめんと ]
バーナーのゴトクの上に置く、金属製の筒状アイテム。バーナーに着火するとヒーターアタッチメントが加熱され、遠赤外線効果で周囲を暖める効果がある。フラットな上部にはケトルなどを置いて湯を沸かすことができるが、安定感をよく確認して活用すること。
ふ
- ファイヤーブラスター
-
読み方 [ ふぁいやーぶらすたー ]
焚き火の際、火力アップのため、ピンポイントで狙った場所に空気を送り込むためのアイテムで、火吹き棒とも言われる。伸縮式で収納時には手のひらサイズになり100均ショップでも手に入る。全長60~80㎝で持ち手部分にウッドを採用した火吹き特化型の1本物、トングになったり火かき棒の機能も付く多機能タイプなど、さまざまなモデルがある。
- ファットウッド
-
読み方 [ ふぁっとうっど ]
燃焼しやすい樹脂を多く含んだ木材のことで、天然の着火剤として使われる。日本各地に多く植林されている「マツ」が一般的である。採取する場合は、大前提としてまず、キャンプ場やその土地の管理者に許諾を得ること。承諾を得たら倒木を探すことから始めよう。マツを見つけたら枝の根本をカット。もし飴色の樹脂の塊が見えたらそれがファットウッドだ。使い方は少量を削ってそこに着火するのみ。火もちがよく、とても優秀。よく燃える素材だがススが多く出るので、あくまでも着火剤と割り切って使おう。
- ファミリーキャンプ
-
読み方 [ ふぁみりーきゃんぷ ]
車で出かけるライトレジャーとキャンプを組み合わせたオートキャンプの文化は、日本のキャンプシーンの中心的存在。その中でもファミリーキャンプの利用者は群を抜いており、週末や大型連休のオートキャンプ場では圧倒的な数を占めている。ファミリーでキャンプに出かける効用は、子どもに対する情操教育としてはもちろん、大人も存分にリラックスしたり、新しい体験にチャレンジするなど、自然での体験を通じてさまざまな気づきに直面できること。何より、キャンプに出かけた家族全員が快適に楽しめれば、キャンプやアウトドアのライフスタイルは一生続けられる遊びとなるはず。
- ファーストエイドキット
-
読み方 [ ふぁーすとえいどきっと ]
フィールドで起こりうる万が一のケガに備えて、キャンプで常備したいのがファーストエイドキットだ。絆創膏、ガーゼ、消毒液、包帯、ポイズンリムーバー、常備薬など、自身や家族に対応するものをまとめ、専用のケースに入れておく。ケースは明るめのものにしておくことと、どこに収納しているかを常に把握しておくことが大事。いざというときにサッと取り出せることが重要だ。
- フィルパワー
-
読み方 [ ふぃるぱわー ]
おもにダウンで使われる「復元力」を指し、1オンス(28.4g)のダウンボールをシリンダーに入れた際の膨らみ具合により、フィルパワーの数値は決められている。略して「FP」とも表記される。600フィルパワーのダウンジャケットなら良質なダウンと言え、街中でのジャケットとしては充分。800フィルパワーとなれば、より空気を多く含む超高品質なダウンのため保温力が高く、寒冷地にも対応できる。数値が大きいほどパフォーマンスは高い。
- 風防
-
読み方 [ ふうぼう ]
バーナー使用時、風の影響による燃料、火力のロスを防ぐ、重要な役割を持つアイテム。一般的なツーバーナーなら、蓋を開けてサイドの風防を広げれば3方向からの風を防ぐことができる。アウトドア用のワンバーナーは基本的に火力が強いため風防は備わっておらず、よほどの強風でない限りは使わずにやりすごせるケースが多い。しかし強風時は不可欠。ちなみにアルコールストーブは特に風に弱く、微風でも湯沸かしや調理時に影響が出るため、使用する際は必ず風防を用意したい。風防には蛇腹の折り畳み式、ロール式のゴトク兼風防や、ネイチャーストーブがそのままアルコールストーブ用の風防として使えるものもある。焚き火台と合わせて使える大型のタイプもあり、そういった製品は風防としての機能に加え、輻射熱でサイトを温める効果も持つ。
- フォーシーズン
-
読み方 [ ふぉーしーずん ]
一年を通じて使用できるキャンプギアの意味。おもにテントで使用される言葉で、インナーテントはメッシュ地ではなく、フライシートにはスカートが付くのが大前提。テント内の保温性を重視するため、スリーシーズンテントに比べると通気性は劣る。そのため結露の発生も多く、状況によってはシュラフカバーなどで寝袋が濡れるのを防ぐ対策が必要なことも。オートキャンプ用のファミリー向けフォーシーズンテントには、そのデメリットを解消すべくインナーテントの素材にポリコットンを採用しているモデルがある。適度に吸湿し、結露の発生を軽減する。
- フライシート
-
読み方 [ ふらいしーと ]
ダブルウォール構造のテントにおける、インナーテントの外側にセッティングする生地のこと。おもに雨などの水濡れからインナーテントを守る役割がある。「アウター」とも呼ばれる。フライシートとインナーテントに隙間を作ることで、そこに空気を循環させ、結露を軽減してくれる。
- フラッシュライト
-
読み方 [ ふらっしゅらいと ]
手持ちタイプのLEDライトの総称。
- フリーサイト
-
読み方 [ ふりーさいと ]
テントやタープなどを設営する場所に決まりがないサイトのこと。キャンプ場によって車の乗り入れが可能な場所、不可能な場所がある。区画がなければどちらも「フリーサイト」。キャパシティが充分にあるキャンプ場では予約不要の場所も多く、急にキャンプに出かけたくなった場合には便利だ。高規格キャンプ場で区画型のオートサイトと車の乗り入れができないフリーサイトが併設してある場合は、多少の不便が生じるため利用料がリーズナブルなパターンがある。レイアウトの自由度が高いのがフリーサイト最大のメリットだが、混雑時期にはスペースを探すのに難儀する可能性が高い。空いているスペースを見つけたとしてもそこは水はけが悪かったり、地面が斜めに傾いていたりと、快適に過ごせないかもしれない。また道具のサイズ感が身に付いていないビギナーにとって、設営する際の隣接サイトに対する気苦労は大きい。慣れないうちは設営スペースがきっちりと定まった区画サイトを選び、キャンプの経験と設営の感覚を身に付けてから、フリーサイトのフィールドに出かけるのがおすすめ。
- フルオープン
-
読み方 [ ふるおーぷん ]
おもにスクリーンタープやシェルター、ツールームテントといった、大型の「ドアパネル」を備える全天候型の幕体における展開パターンのひとつ。すべてのドアパネルを開けて、屋根下の空間を開放すること。
- フルクローズ
-
読み方 [ ふるくろーず ]
おもにスクリーンタープやシェルター、ツールームテントといった、大型の「ドアパネル」を備える全天候型の幕体における展開パターンのひとつ。すべてのドアパネルを閉じることで、風雨から室内空間を守る。
- フルフラット
-
読み方 [ ふるふらっと ]
車中泊をする際、車のシートを倒してフラットなスペースに展開するシートアレンジのこと。マットレスやブランケットなどで凹凸を解消し、できる限りフラットにして快適なベッドスペースを作る。車種によってフルフラットの方法は異なるが、大抵の場合、後席のシートを跳ね上げたラゲッジスペースが、最も簡単なフルフラットなスペースといえる。
- フルメッシュ
-
読み方 [ ふるめっしゅ ]
スクリーンタープやシェルター、ツールームテントといった、大型の「ドアパネル」を備える全天候型の幕体における展開パターンのひとつ。すべてのドアパネルをメッシュ地にして、屋根下の空間に通気性を確保しながら虫の侵入を防ぐスタイル。
- フレームワーク
-
読み方 [ ふれーむわーく ]
テントなどのフレーム構造のこと。最も基本的なドームテントの構造である2本のフレームをクロスして自立させる「クロス型」は、シンプルなので設営は楽で居住空間が広い。「魚座型」は2カ所を交差させるためクロス型よりも強度が増した構造。「モノポール型」はポール1本で設営できる説明不要の手軽さが特徴。大きくなるほどペグダウンポイントは多くなる。「ロッジ型」は直線的なフレームを組み合わせて広い居住空間を作る。フレームが多くなるためオートキャンプに向いている。「A型」はシンプルな構造なので設営は簡単。側面が斜めになるため居住空間が手狭に感じることも。またハブ構造を採用し、広い空間を持つ実用性の高さと美しいデザインの独創性を兼備するハイスペックモデルも数多い。一般的に、壁面に立ち上がりがある直線的な「フレームワーク」のテントは室内が広く、デッドスペースは少ない。
へ
- ヘッドランプ
-
読み方 [ へっどらんぷ ]
頭に装着するLEDを光源とするランプ。視線を向けた先が照らされて夜間でも安心して行動できる他、夕食の調理時などは、両手が空くため作業をスムーズにこなせる。バッテリー内蔵式と電池式がある。LEDランタンと併せて、キャンプの夜の必需品。
ほ
- 琺瑯
-
読み方 [ ほうろう ]
鉄やアルミニウムなどの金属の表面にガラス質の釉薬を高温で焼き付けたもの。光沢があり見た目がいいだけでなく、耐久性、耐熱性、保温性に優れた素材。ケトル、カップなどの食器、保存容器に加え、ダッチオーブンまである。
- 火口
-
読み方 [ ほくち ]
メタルマッチなどの火花で着火する燃えやすい材料。ティンダーとも呼ぶ。代表的なものは麻紐を繊維状にほぐしたもので、100均ショップなどでも手に入り、使いやすい。普段持ち歩いているティッシュペーパーも火口として利用できる。自然にあるものを利用するなら、油分を多く含んだスギの皮を手でよく揉んで繊維状にする。少し湿っていても、擦る摩擦で乾燥させればいい。ナイフがあれば、木の枝を薄く削り出してカールさせるフェザースティックも火口になる。ただし、その場合はかなり薄く削る必要がある。
- ホットサンドメーカー
-
読み方 [ ほっとさんどめーかー ]
ホットサンドを作るのに適した2枚の同型鉄板を組み合わせたクッカー。ベーシックな使い方としては食パンの上に好きな食材を置き、その上に食パンを載せて挟んで閉じて両面を加熱する方法だ。この調理器具は食パンに限らず、肉まんや餃子、お好み焼き、おにぎりなどさまざまな料理に応用でき、新しい美味しさを発見できる。鉄製のタイプなら焚き火で豪快に使えるし、2枚を分割できるタイプならそれぞれをフライパンとして使ってもいい。
- ホヤ
-
読み方 [ ほや ]
ランタンの光源を保護すると同時に、光の強さをやわらげて拡散させる役割を持つ、筒状のカバー。グローブとも呼ばれる。マントルを光源とする燃焼式ランタンでは、マントルが破けるのを防ぐ意味合いも強い。
- ホワイトガソリン
-
読み方 [ ほわいとがそりん ]
自動車燃料の赤ガスに対して、ホワイトガソリンは白ガスとも呼ばれる。ホワイトガソリンは原油精製の過程で得られる無添加、無着色のガソリン。機械などの洗浄油としても使用される。コールマンの純正ホワイトガソリンは、さらに精製して人体や自然に有害な物質をすべて排除した環境対応型。他の燃料と区別するため「青色」に着色されている。こちらは燃焼効率が高く、カーボンの発生を抑えられるため、器具が目詰まりを起こしにくいのが特徴。
ま行
ま
- 薪
-
読み方 [ まき ]
焚き火をする際の主要燃料。キャンプ場の大半で販売されている他、ホームセンターでも手に入る。大きく針葉樹と広葉樹に分類される。針葉樹はスギ、マツ、ヒノキなどで、密度が低く軽量なため比較的簡単に割ることが可能。着火は容易で焚き火の焚き付けとして優れている。スギとマツは油分が多くよく燃えるが、その分ススも出る。ヒノキは針葉樹の中では火もちがよく、香りもいい。対して広葉樹は密度が高くずっしりと重量がある。針葉樹に比べて樹脂量は少ないが、格段に火もちがいい。安定した火力を長時間キープできるため、じっくりと焚き火&調理を楽しむなら広葉樹が断然おすすめ。広葉樹の薪で代表的なのはナラ(オーク)で、最も流通が多い。サクラはスモークチップやウッドにも使用される材で、燃焼時にいい香りが出るのが特徴だが、燃焼のパフォーマンスはナラに比べて劣る。高級家具などにも使われるケヤキは広葉樹の中では着火しやすいのが特徴。その他、高級な位置付けの広葉樹の薪はカシ、クヌギ。特にカシはプレミアムな薪として知られ、火もちもよい。クヌギはほのかな香りと火もちのよさが人気。
- 薪の組み方
-
読み方 [ まきのくみかた ]
着火時において最も重要なのは空気の流れ。薪同士は適度な隙間を開けることでスムーズな燃焼が可能となる。手っ取り早く多くの薪に着火させたいのなら、キャンプファイヤーなどでおなじみの「井げた型」がおすすめ。組むのも着火するのも簡単だ。「合掌型」は傘のように立てる組み方で、ティピー型とも呼ばれる。大きな火を作るのに適しているが、組み方にはコツが必要。直焚き火なら薪を地面に刺すなどして安定が図りやすいが、焚き火台は火床のサイズ、形状によって難易度が変わる。難しい場合は他の組み方にシフトしよう。「差し掛け型」は、1つの大きめの薪を枕代わりにし、そこに他の薪を差し掛ける組み方。これは直焚き火でも焚き火台でも火床の状況にかかわらず組みやすく、下部に適度な空間ができるため着火もしやすい。燃え広がり方もゆるやかで火力コントロールが楽なので、初めての焚き火ならまずは差し掛け型でチャレンジするのがおすすめ。
- 薪ストーブ
-
読み方 [ まくすとーぶ ]
薪を燃料とし、箱型の燃焼室で燃焼させるストーブ。寒い時季にはテント内に入れ、煙突を装着して外に排気する。素材は鉄製、ステンレス製の重厚なものから、バックパッキングができるほど軽量でコンパクトなチタン製もある。耐熱ガラスを採用しているタイプなら炎の様子を眺められる上、遠赤外線効果によって保温性も上がる。本体上部のフラットなスペースは調理の熱源として活躍。じっくりと煮込む料理を作ったり、ケトルの湯を沸かしたりするのに適している。直火ではないためクッカーにススが付くこともない。薪ストーブの煙突には本体の上出し、横出しの2タイプがあり、薪ストーブをテント内に設置する上で「テントのどこから煙突を出すか」が重要なポイントとなる。煙突は非常に高温になるため、テント生地と接する部分には煙突ガードなどの加工が必要だ。煙突の本体に近い側には火力をコントロールするダンパー(弁)が付いているモデルがあり、閉じれば火力をセーブし、開ければ火力をアップできる。ダンパーを閉じ溜ままにしたり、燃焼室に炭や灰がたまると煙が逆流することもあるため、定期的に奥側から火かき棒で灰をかき出して詰まりを抑制するなどの確認が必要。万が一の事故を防ぐため、一酸化炭素チェッカーの併用は必須だ。
- マグカップ
-
読み方 [ まぐかっぷ ]
取っ手の付いた、おもに飲み物を飲むためのカップ。家庭向けなら陶器も含まれるが、キャンプでのマグカップといえば耐久性が高いステンレス、チタンなどが挙げられる。軽量な1層のシングルタイプに比べ、2層のダブルウォールタイプもあり、保温性が高いのが特徴。冷たい飲み物を入れてもぬるくなりにくく、逆に熱い飲み物を入れても冷めにくい。
- マットレス
-
読み方 [ まっとれす ]
キャンプで地面の凹凸や熱気・冷気を遮断して快適な眠りにつくための重要なアイテム。広げるだけで瞬時に展開できるクローズドセルタイプと、空気で膨らませ、収納時にはコンパクトになるインフレータブルタイプがある。対応温度の目安を知る数値としては、R値が挙げられ、厚さや素材によって変わる。登山などのバックパッキングでは極力軽量でコンパクトなモデルが求められるが、オートキャンプ仕様となれば、ある程度「どこまで快適に眠れるか」が優先されるだろう。車載や携行性との相談になるが、厚さが10㎝もあるマットレスなら寝心地は極上。ただし、収納状態はそれなりのサイズとなる。インフレータブルタイプには収納袋を空気入れにできたり、フットポンプを内蔵するモデルもある。
- マルチプライヤー
-
読み方 [ まるちぷらいやー ]
用途としては万能ナイフとほぼ同じだが、プライヤーを主としたレザーマンに代表される万能ツールはキャンプでの有用性が高い。コンパクトではあるが、それぞれの持つ機能を十二分に発揮。重厚でタフなイメージのモデルが多く揃う。マルチツールとも呼ぶ。
- マントル
-
読み方 [ まんとる ]
燃焼式ランタンの光源、発光体。もとは化学繊維を袋状に編んだもので、引っ張っても強度はあるが、使用の際はライターなどでマントル全体を燃やす空焼きという作業を経て灰状にする。空焼き後のマントルは非常にもろく破けやすいため、触ってはならない。消耗品で定期的な交換が必要だが、よほど乱暴に扱わない限り、頻繁には破けない。マントルの一部が破けたまま燃焼し続けると、破けた穴部分から漏れた炎がガラス製グローブの1点に集中し、割れてしまうことがある。使用前にマントルの様子を確認し、破けているようならすぐに交換しよう。
み
- ミルスペック
-
読み方 [ みるすぺっく ]
アメリカ軍が必要とする物資の調達に使用されている規格で、「MIL規格(Unitedstatesmilitarystandard=MIL-STD)」とも呼ばれる。ミルスペックとして認められた製品は過酷な自然環境においても機能を損なわず、正真正銘「タフ」の証だということ。テントなどのキャンプ道具をはじめ、ウエアやバックパック、腕時計、サングラス、ブーツなどの他、スマートフォンやノートPCといったデジタルガジェットも存在する。
め
- メスティン
-
読み方 [ めすてぃん ]
飯盒の一種で、飯盒を英訳すると「Messtin(メスティン)」。アウトドアやキャンプにおいては、ピンポイントで長方形のアルミ製クッカーを指す。本来はトランギア製のオリジナルが「メスティン」の名称で販売されていた。近年その使い勝手のよさから注目を浴び、固形燃料での自動炊飯の他、多種多彩なレシピが考案される。本家以外にも多くのアウトドアメーカー、ホームセンターや100均ショップがオリジナルのメスティンを発売するなど、人気は過熱。焦げ付きにくいアルマイト加工を施したモデルもある。スタッキングできる鉄板やまな板といったオプションアイテムも豊富。
- メタルマッチ
-
読み方 [ めたるまっち ]
可燃性の高い棒(ロッド)をストライカーで素早くこすり、火花を散らして火種を作る道具。ファイヤースターターとも呼ばれる。ロッドの素材はおもにマグネシウムとフェロセリウムの2種で、フェロセリウムのほうが引火点が低く火花を飛ばしやすい。ライターやマッチを使わず、メタルマッチで焚き火に着火する際は麻紐などの火口を用意し、そこにロッドから金属を少量削り落としたのち、冒頭の方法で火口に着火する。火花の温度は3000℃近くの高温で、濡れていなければ気温に関係なく使用できる。ホワイトガソリン式など、点火装置がないバーナーにも着火アイテムとして使用可能である。
- メッシュパネル
-
読み方 [ めっしゅぱねる ]
テントやスクリーンタープなどのドアパネルに配されたメッシュ生地のこと。通気性を確保しながら幕内に虫が侵入するのを防ぐ。テントの下部、上部にベンチレーション用のメッシュパネルが装備されているものもある。
- メッシュポケット
-
読み方 [ めっしゅぽけっと ]
インナーテントの枕元やコットやチェア、ハンモックのサイドなどにあるメッシュ状の小物入れ。テントのメッシュポケットに指輪を入れたまま畳んだり、チェアのメッシュポケットにスマートフォンを入れっぱなしにして収納袋に入れて車載してしまうなど、小物紛失のエピソードが多数生まれるポイントでもある。とても便利なポケットで視認性がいい作りなので、撤収の前には取り忘れがないように確認しよう。
や行
や
- 野営
-
読み方 [ やえい ]
キャンプ場ではないところを宿泊地とすること、またはその行為。海にカヤックで出かけて無人のビーチでキャンプをしたり、カヌーで川を下りながら途中で上陸してベースを作る行為も含まれる。なお、無人島は冒険好きにとって憧れの的だが、実際のところ誰かしらの持ち物。つまりキャンプをするには許可が必要。沖縄や四国、奄美など、キャンプができる無人島は多く存在しているが、事前に調べてから問い合わせをしてみよう。河川に関しては河川法の第24条が定めるところによると「自由使用」が認められている(管理区域を除く)。よって安全な場所を見つけての野営は問題なし。それでも野営してよいかどうか気になる場合は、その土地の自治体に問い合わせてみよう。
ゆ
- UL
-
読み方 [ ゆーえる ]
ウルトラライト
よ
- ヨーロピアン・ノーム
-
読み方 [ よーろぴあん・のーむ ]
EU諸国における、寝袋の温度表記に関する統一規格。いずれの製品にも「COMFORT」「LIMIT」「EXTREME」の3段階で表示されており、寝袋を選ぶ際の目安としてしっかり確認したいポイント。COMFORTは一般的な成人女性が寒さを感じず快適に眠れるであろう温度域。LIMITは一般的な成人男性が寝袋の中で丸くなり8時間眠れる温度域。EXTREMEは、一般的な成人女性が寝袋の中で丸くなり6時間耐えられる温度域。寒さの感じ方には個人差があるため、絶対的なものではなくあくまでも目安としてとらえること。
ら行
ら
- ライスクッカー
-
読み方 [ らいすくっかー ]
米を炊くことに特化した鍋。一般的には熱伝導のよいアルミ製で、密閉できる蓋が付く。飯盒やメスティと比較すると素材に厚みがあるものが多く、蓄熱性もあるため、ふっくらと美味しい炊き上がりになる。
- ラウンド
-
読み方 [ らうんど ]
ヘキサタープやウイングタープなどを張ったときの、中心の縫い目の形状のこと。稜線とも呼ばれ、きれいにタープを設営できると美しい形状となる。
- ラフティング
-
読み方 [ らふてぃんぐ ]
ラフトボートに乗り、おもに川の急流を下るアクティビティ。一般的にはガイドツアーに参加し、適切なガイド指導のもとで体験するプログラム。安全のためヘルメットとPFDを装着し、シングルパドルで漕ぎ進む。
- ランタンシェード
-
読み方 [ らんたんしぇーど ]
ランタンの笠のこと。既存のランタンに追加することで明かりを下方へ集中させる。リビングなどで使用する場合は、ランタンをできる限り上に配置する。燃焼式ランタンには熱に強い金属製が使われ、LEDランタンでは大型から小型までさまざまなサイズが揃っている。デザインのアクセントにもなるため、好みの製品を探すのも楽しい。
- ランタンハンガー
-
読み方 [ らんたんはんがー ]
ランタンを吊るす、もしくは引っ掛ける用途に特化したハンガーのこと。支柱を地面に差し込むタイプ、収束式の脚を広げて自立するタイプ、テーブルなどの天板にクランプ留めをするタイプなどバリエーションは豊富。
り
- リビングテーブル
-
読み方 [ りびんぐてーぶる ]
サイトのリビングスペースで扱うのに適したテーブル。おもに人数に応じた天板サイズを持つメインテーブルとしての意味合いを持つ。人数分の食器を置くことができ、リビングの中心に配置するイメージ。ファミリー向けの大型タイプなら、ハイとローの2段階の高さに調節できるタイプが主流。チェアに合わせて最適な高さに設定できる。
る
- ルーフトップテント
-
読み方 [ るーふとっぷてんと ]
車のルーフに設置するテントのことで、ソフトシェルタイプとハードシェルタイプがある。走行時は薄く格納されており、広げれば瞬く間にセットアップが完了。ほとんどのモデルにはマットレスも内蔵されており、あとは気温に応じた寝具を用意すればよい。地面にセットするテントと比べて圧倒的に早い設営と撤収を可能にしている。省スペースでキャンプができ、片付けもスピーディなためアクティブ派にはうってつけ。コンパクトなものからファミリー向けまで、サイズ展開も豊富だ。
れ
- 冷燻
-
読み方 [ れいくん ]
燻製法の一種。15℃~30℃の低温で長時間じっくりと食材を燻煙する方法で、冷燻で作られる代表的なものとしてはスモークサーモンやビーフジャーキーが挙げられる。温度管理が難しく長時間かかるため、キャンプで気軽にはできない。時間をかけて食材の水分を抜いて燻煙するため、冷燻で仕上がったものは長期保存に向いている。
- レイヤード
-
読み方 [ れいやーど ]
快適に過ごすために衣類を重ね着すること。肌着のベースレイヤー、中間着のミドルレイヤー、上着のアウトレイヤーの3レイヤーが基本的な考え。天候や気温の変化によって脱ぎ着し、体をドライに快適な状態に保つ。日本発のアウトドアブランド・ファイントラックは従来の3レイヤー発想を覆し、より肌をドライに保つ5レイヤーを提唱している。
- レギュレーター
-
読み方 [ れぎゅれーたー ]
2008年4月に発売を開始した、SOTOのガス式ワンバーナー「レギュレーターストーブST-310」に搭載された、従来型CB缶式バーナーの宿命ともいえるドロップダウン現象を解消する画期的システム。正しくはマイクロレギュレーターだが、製品名が先行してかマイクロを省略して称される。
- 連結
-
読み方 [ れんけつ ]
テントとタープ(スクリーンタープやシェルターも含む)をつなげて居住性を高めるレイアウト。2010年ごろから、ファミリーキャンプで使用する大型のドームテントとスクリーンタープを縦型に連結するスタイルが浸透。この時期は複数のメーカーが連結対応のテントをリリースしていた。雨天時、寝室とリビング間の移動で濡れることなく、小さな子どもを持つファミリーにとってはどこでも立って移動ができる。とにかく広々と過ごせる定番のスタイルの1つだったが、ロースタイル&コンパクト化やツールームテント、トンネル型テントの台頭により、連結ブームは徐々に下火になる。現在でも根強い人気を誇る連結スタイルの1つが小川張りだ。
ろ
- ロケットストーブ
-
読み方 [ ろけっとすとーぶ ]
煙突効果を利用した高火力が自慢の、調理特化型のネイチャーストーブ。薪ストーブでいう煙突の出口に二次燃焼の炎が上がり、高火力を生み出す仕組みだ。中華鍋と組み合わせて強火で料理するのもあり。箱型の本体を持つタイプなら、箱の天板を弱火で保温エリアとして使える。自然素材を使って高効率で燃焼できるため、災害時にも役立つアイテム。構造上、暖をとることにはさほど特化していない。
- ロストル
-
読み方 [ ろすとる ]
BBQグリルや焚き火台の火床に置く台座。耐久性に優れる素材で焚き火台では抜群の強度と安定感を持つ。下部からの空気を導入しやすくして燃焼効率を高める役割もある。
- ロッキーカップ
-
読み方 [ ろっきーかっぷ ]
シェラカップを大きくしたもので、フォルムはすり鉢状ではなく、ストンと寸胴のよう。容量は1パイント(アメリカ基準)・約473㎖が基準で、炊飯やラーメンを作るのにも便利なサイズ。さらに底面はシェラカップよりも広いためバーナーのゴトクに載せても安定しやすく、とにかく汎用性が高い。素材はおおむねステンレス、チタンが占める。現在は廃番となっている。
- ロフト
-
読み方 [ ろふと ]
寝袋やダウンジャケットなどで使う専門用語で、ふわふわなダウンにより発生する「かさ」のこと。ロフトがある製品ほど空気を多く含み復元力が大きく、保温力も高い。ダウン寝袋をコンプレッションバッグに入れて長期間保管するとロフトは不足する。
- ローインパクト
-
読み方 [ ろーいんぱくと ]
指定場所以外でのキャンプを行わない。食器洗いには中性洗剤を使わないなど、人間が自然の中で活動する上で、極力自然環境に負担をかけない考え方。たとえ整備されたキャンプ場でも心がけは重要。宿泊したキャンプサイトはきちんと元通りにしているか? 直火サイトでの焚き火はきちんと燃やし切ることを心掛けているか? 燃え残りはそのままにせず、持ち帰って再利用に備えているか?など、さまざまな配慮を忘れないこと。
- ロースタイル
-
読み方 [ ろーすたいる ]
キャンプサイトにセッティングするファニチャー類を基準とし、他のアイテムも低くセッティングして楽しむキャンプスタイルのこと。スタイリッシュにまとまると同時に、耐風性が高まるメリットもある。しかしときにタープの屋根下空間が低く、屈んで移動しなくてはならなかったり、立つ&座る動作が億劫だったりと、過ごしてみれば意外と弊害もある。そのようなユーザーニーズに応え、多くのファニチャーでは脚のパーツの調節により高さを変えられるものが多くリリースされている。そのときの気分や状況に応じてハイスタイルでもキャンプを楽しめる。
- ローテーブル
-
読み方 [ ろーてーぶる ]
おもにロースタイルで使用するテーブル全般。天板地上高が40㎝前後のものから限りなく地面に近いコンパクトなタイプまで含まれる。ウッド、耐熱ステンレス、アルミなど、素材の種類は数多く、1~2名対応のものなら収納はそれほど大きくない。そのため複数を組み合わせて持っておくことが実用面では好ましく、シーンに応じて展開や組み合わせをアレンジできる。たとえば焚き火のサイドテーブルとして単体で使うことがあれば、合体させて食卓テーブルにしたりといった具合。コンパクトなのでキャンプサイトでの移動やレイアウト変更も大した労力ではない。
- ロープワーク
-
読み方 [ ろーぷわーく ]
キャンプで必要とされるロープワークはそう多くない。覚えておけばキャンプで役に立ちそうなロープワークを5種紹介する。「キングオブノット」と称される「もやい結び」は、使う頻度が低いと意外に忘れてしまう結び。経験者でも心当たりがある人も多いだろう。ここではあえて、より簡単で使いやすい結びをセレクトしている。
検索したワードを含むキャンプ用語はありません。